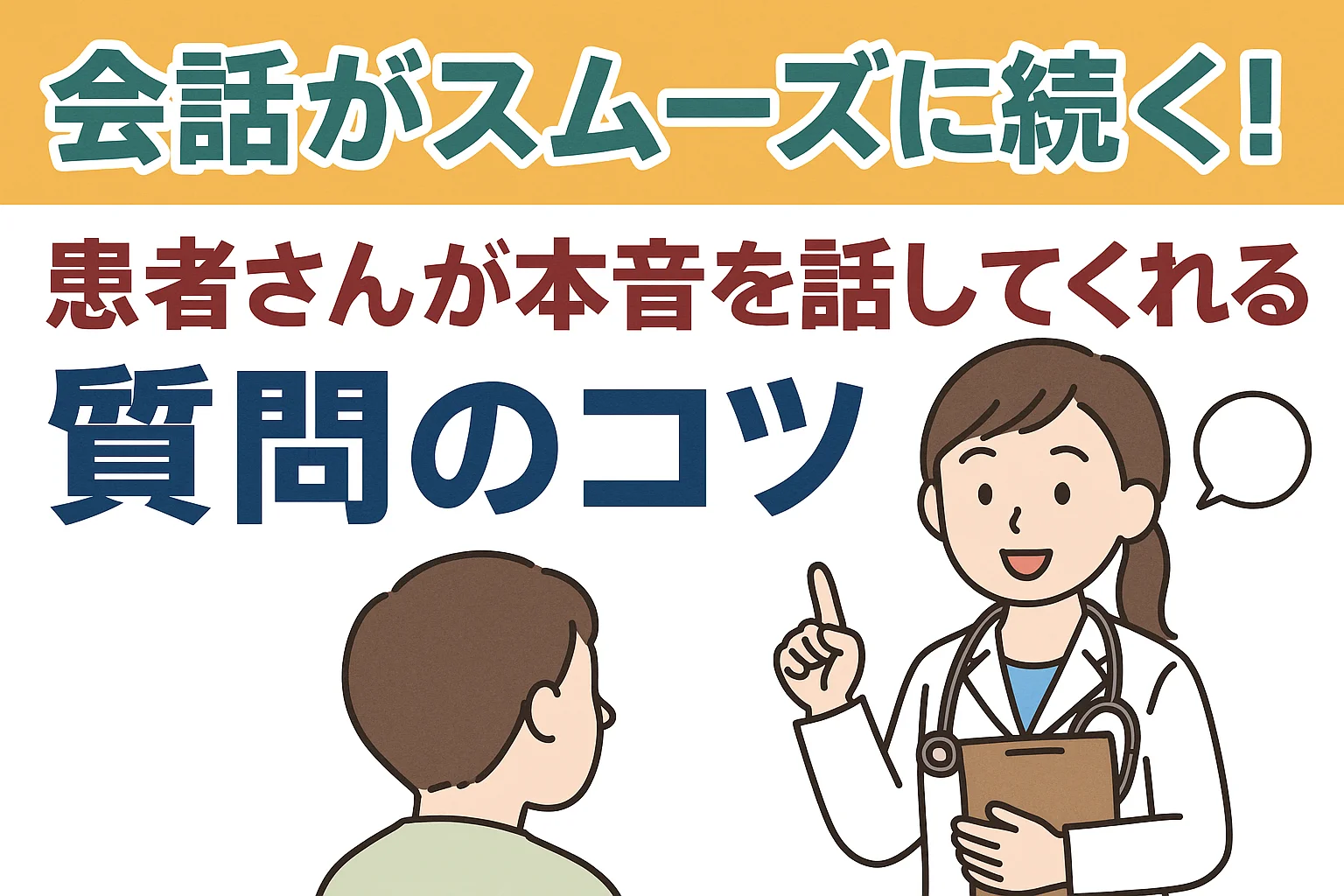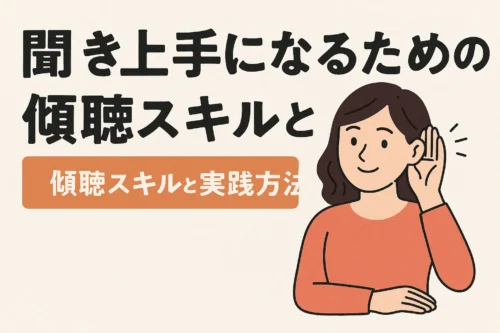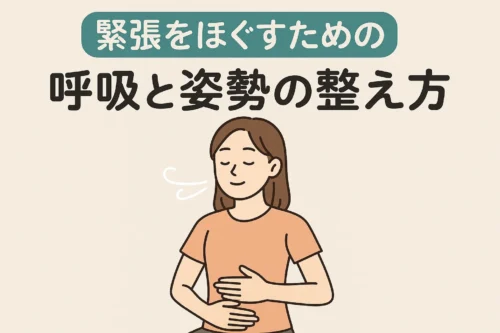毎日40人・年間1万人以上と会話しているRyoです。
薬局で患者さんと話していると、質問の仕方一つで、患者さんの反応が全く変わってしまうことに気づいたんです。同じことを聞くにしても、質問の仕方によって、患者さんが心を開いてくれるかどうかが決まってしまうんですよね。
ある患者さんに「この薬、飲み忘れはありませんか?」と聞いた時は、患者さんは「大丈夫です」とだけ答えて終わってしまいました。しかし、別の日に「この薬を飲む時に、何か困ったことはありませんか?」と聞いた時は、患者さんが「実は、朝忙しくて飲み忘れることがあるんです」と、本音を話してくれたんです。
これって、質問の仕方によって、患者さんの心の扉が開くかどうかが決まるということなんです。だからこそ、相手の心を掴む質問力を身につけることが、非常に重要になってくるんです。
なぜ質問力が重要なのか
質問は会話の鍵
質問は、会話を深め、相手の心を開かせるための鍵です。適切な質問をすることで、相手は自分の考えや感情を整理し、より深い話をすることができるようになります。
薬局では、患者さんの症状や生活環境、薬の服用状況などを把握するために、質問が不可欠です。しかし、質問の仕方によって、患者さんが心を開いてくれるかどうかが決まってしまうんです。
信頼関係の構築に不可欠
適切な質問をすることで、相手は「この人は私のことを理解しようとしてくれている」と感じ、信頼感を持つようになります。
薬局では、患者さんとの信頼関係が薬の服用率に直結します。信頼できる薬剤師の質問なら、患者さんは本音で答えてくれるんです。
問題解決の第一歩
適切な質問をすることで、その人が本当に困っていることや、本当に必要としていることがわかるようになります。
薬局では、患者さんの症状だけでなく、生活環境や家族の状況、仕事のストレスなども含めて総合的に判断する必要があります。質問力があることで、これらの情報を自然に聞き出すことができるんです。
薬局での実際の体験談
質問の仕方で患者さんの心を開かせた時
ある日、高血圧の薬を処方された患者さんが来店したんです。最初は「この薬、副作用はありますか?」と聞かれたので、一般的な副作用について説明しました。
しかし、その後「この薬を飲む時に、何か困ったことはありませんか?」と質問してみたんです。すると、患者さんは「実は、朝忙しくて飲み忘れることがあるんです。でも、夜に飲んでも大丈夫でしょうか?」と、本音を話してくれました。
この質問によって、患者さんの本当の悩みがわかったので、朝の忙しい時間でも飲み忘れないような工夫や、夜に飲んでも問題ないことを説明することができました。
質問の仕方が悪くて患者さんが心を閉ざした時
別の患者さんで、風邪薬を処方された方がいたんです。その患者さんに「この薬、飲み忘れはありませんか?」と聞いた時、患者さんは「大丈夫です」とだけ答えて、それ以上話してくれませんでした。
後で気づいたのですが、この質問は「飲み忘れをしていないか」を確認する質問で、患者さんが「はい」「いいえ」で答えられるクローズドクエスチョンだったんです。
もし「この薬を飲む時に、何か困ったことはありませんか?」と聞いていれば、患者さんはもっと詳しく話してくれたかもしれません。
効果的な質問の種類
1. オープンクエスチョン
オープンクエスチョンは、相手が自由に答えられる質問です。相手の考えや感情を深く理解することができます。
実践例:
- 「どう思いますか?」
- 「どのように感じましたか?」
- 「何か困ったことはありませんか?」
- 「どのような状況ですか?」
2. クローズドクエスチョン
クローズドクエスチョンは、相手が「はい」「いいえ」で答えられる質問です。確認や同意を得る時に使用します。
実践例:
- 「この薬は飲み忘れはありませんか?」
- 「副作用は出ていませんか?」
- 「体調は良くなりましたか?」
3. 選択肢のある質問
選択肢のある質問は、相手に選択肢を与える質問です。相手が答えやすい質問です。
実践例:
- 「朝と夜、どちらの方が飲みやすいですか?」
- 「錠剤と粉薬、どちらが飲みやすいですか?」
- 「食前と食後、どちらの方が飲みやすいですか?」
4. 深掘り質問
深掘り質問は、相手の話をより詳しく聞くための質問です。相手の話を深めることができます。
実践例:
- 「それで、どうなりましたか?」
- 「その後は?」
- 「具体的には、どのような状況ですか?」
- 「なぜ、そう思ったのですか?」
相手の心を掴む質問のコツ
1. 相手の立場に立って質問する
相手の立場に立って質問することで、相手は「この人は私のことを理解しようとしてくれている」と感じ、心を開いてくれます。
実践例:
- 患者さんの生活環境を考慮した質問をする
- 患者さんの気持ちに共感した質問をする
- 患者さんの立場に立った質問をする
2. 相手の話を聞いてから質問する
相手の話をしっかり聞いてから質問することで、相手は「この人は私の話を聞いてくれている」と感じ、より詳しく答えてくれます。
実践例:
- 相手の話が終わるまで待つ
- 相手の話の内容を理解してから質問する
- 相手の感情を理解してから質問する
3. 相手のペースに合わせて質問する
相手のペースに合わせて質問することで、相手はリラックスして答えることができます。
実践例:
- 相手の話すスピードに合わせる
- 相手の反応を見ながら質問する
- 相手が考えやすい質問をする
4. 相手の興味を引く質問をする
相手の興味を引く質問をすることで、相手は積極的に答えてくれます。
実践例:
- 相手が関心を持っている話題について質問する
- 相手の経験や知識を活かした質問をする
- 相手が答えやすい質問をする
質問で避けるべきこと
1. 詰問調の質問
詰問調の質問は、相手を追い詰めてしまい、心を閉ざしてしまいます。
避けるべき例:
- 「なぜ、そんなことをしたのですか?」
- 「どうして、そう思うのですか?」
- 「いつから、そうなったのですか?」
良い例:
- 「どのような理由で、そうしたのですか?」
- 「どのような考えで、そう思うのですか?」
- 「どのような経緯で、そうなったのですか?」
2. 相手を責める質問
相手を責める質問は、相手を傷つけてしまい、関係性を悪化させてしまいます。
避けるべき例:
- 「あなたが悪いのではないですか?」
- 「なぜ、もっと早く来なかったのですか?」
- 「どうして、そんなことをしたのですか?」
良い例:
- 「どのような状況だったのですか?」
- 「どのような理由で、来られなかったのですか?」
- 「どのような考えで、そうしたのですか?」
3. 相手のプライバシーに踏み込む質問
相手のプライバシーに踏み込む質問は、相手を不快にさせてしまいます。
避けるべき例:
- 「年収はいくらですか?」
- 「家族の詳細を教えてください」
- 「個人的な問題について教えてください」
良い例:
- 「一般的な生活環境について教えてください」
- 「家族の状況について、必要に応じて教えてください」
- 「仕事や生活で困っていることはありませんか?」
質問のタイミング
1. 相手の話が終わってから質問する
相手の話が終わってから質問することで、相手は「この人は私の話を聞いてくれている」と感じ、より詳しく答えてくれます。
実践例:
- 相手の話が終わるまで待つ
- 相手の話の内容を理解してから質問する
- 相手の感情を理解してから質問する
2. 相手が考えやすいタイミングで質問する
相手が考えやすいタイミングで質問することで、相手はより詳しく答えてくれます。
実践例:
- 相手がリラックスしている時に質問する
- 相手が時間に余裕がある時に質問する
- 相手が集中できる環境で質問する
3. 相手が答えやすいタイミングで質問する
相手が答えやすいタイミングで質問することで、相手はより積極的に答えてくれます。
実践例:
- 相手が話しやすい雰囲気の時に質問する
- 相手が関心を持っている時に質問する
- 相手が経験を共有したがっている時に質問する
質問の順序
1. 一般的な質問から始める
一般的な質問から始めることで、相手はリラックスして答えることができます。
実践例:
- 「今日は体調はいかがですか?」
- 「何かお困りのことはありますか?」
- 「お手伝いできることはありますか?」
2. 具体的な質問に進む
一般的な質問の後、具体的な質問に進むことで、相手の話を深めることができます。
実践例:
- 「具体的には、どのような状況ですか?」
- 「どのような症状が出ていますか?」
- 「どのような生活をされていますか?」
3. 深掘り質問で締める
最後に深掘り質問をすることで、相手の話をより詳しく聞くことができます。
実践例:
- 「なぜ、そう思ったのですか?」
- 「どのような影響がありますか?」
- 「今後、どのようにしたいですか?」
質問力を高めるトレーニング方法
1. 日記を書く
一日の終わりに、その日した質問を振り返って日記に書くことで、質問力を向上させることができます。
実践例:
- その日した質問の内容を記録する
- 質問に対する相手の反応を記録する
- 改善点を見つける
2. ロールプレイをする
友人や家族と協力して、ロールプレイをすることで、質問力を練習できます。
実践例:
- 質問役と回答役を交代で演じる
- フィードバックをもらう
- 改善点を意識して練習する
3. 専門書を読む
質問力に関する専門書を読むことで、理論的な知識を身につけることができます。
おすすめの本:
- 『質問力』
- 『聞く技術』
- 『カウンセリングの基本』
質問力がもたらす効果
1. 人間関係の改善
質問力を身につけることで、家族、友人、同僚との関係が改善されます。
2. 仕事の効率向上
職場で質問力を活用することで、チームワークが向上し、仕事の効率が上がります。
3. 自己成長
相手の話を聞くことで、新しい知識や視点を得ることができ、自己成長につながります。
4. ストレス軽減
相手の話を聞くことで、相手のストレスが軽減され、結果として自分のストレスも軽減されます。
質問力を活用した接客術
1. 患者さんの話を聞く時間を作る
薬局では、薬の説明だけでなく、患者さんの話を聞く時間を作ることが大切です。
実践例:
- 患者さんが来店したら、まずは体調を聞く
- 薬の説明の後は、患者さんの不安や疑問を聞く
- 必要に応じて、患者さんの生活環境や家族の状況も聞く
2. 患者さんの感情に共感する
患者さんの感情に共感することで、より良い関係を築くことができます。
実践例:
- 患者さんが不安そうにしている時は「心配ですよね」と共感する
- 患者さんが喜んでいる時は「良かったですね」と一緒に喜ぶ
- 患者さんが落ち込んでいる時は「お疲れ様です」と労う
3. 患者さんの話を要約して確認する
患者さんの話を要約して確認することで、理解度を高めることができます。
実践例:
- 「つまり、○○ということですね」
- 「確認させていただきますが、○○で合っていますか?」
- 「まとめると、○○ということですね」
まとめ
質問力は、相手の心を掴むために不可欠なスキルです。薬局での接客を通じて、その重要性を実感しています。
具体的には:
- オープンクエスチョン、クローズドクエスチョン、選択肢のある質問、深掘り質問を組み合わせる
- 相手の立場に立って質問する
- 相手の話を聞いてから質問する
- 相手のペースに合わせて質問する
これらの方法を実践することで、相手の心を開かせ、より良い関係を築くことができます。
ただし、質問力を身につけるには時間がかかります。焦らずに、少しずつ練習していくことが大切です。
質問力が身につくと、人間関係が改善され、仕事の効率も向上し、自己成長にもつながります。ぜひ、日常のコミュニケーションで実践してみてくださいね。
薬局での接客を通じて、質問力の大切さを学びました。皆さんも、相手の心を掴む質問から始めてみてください。