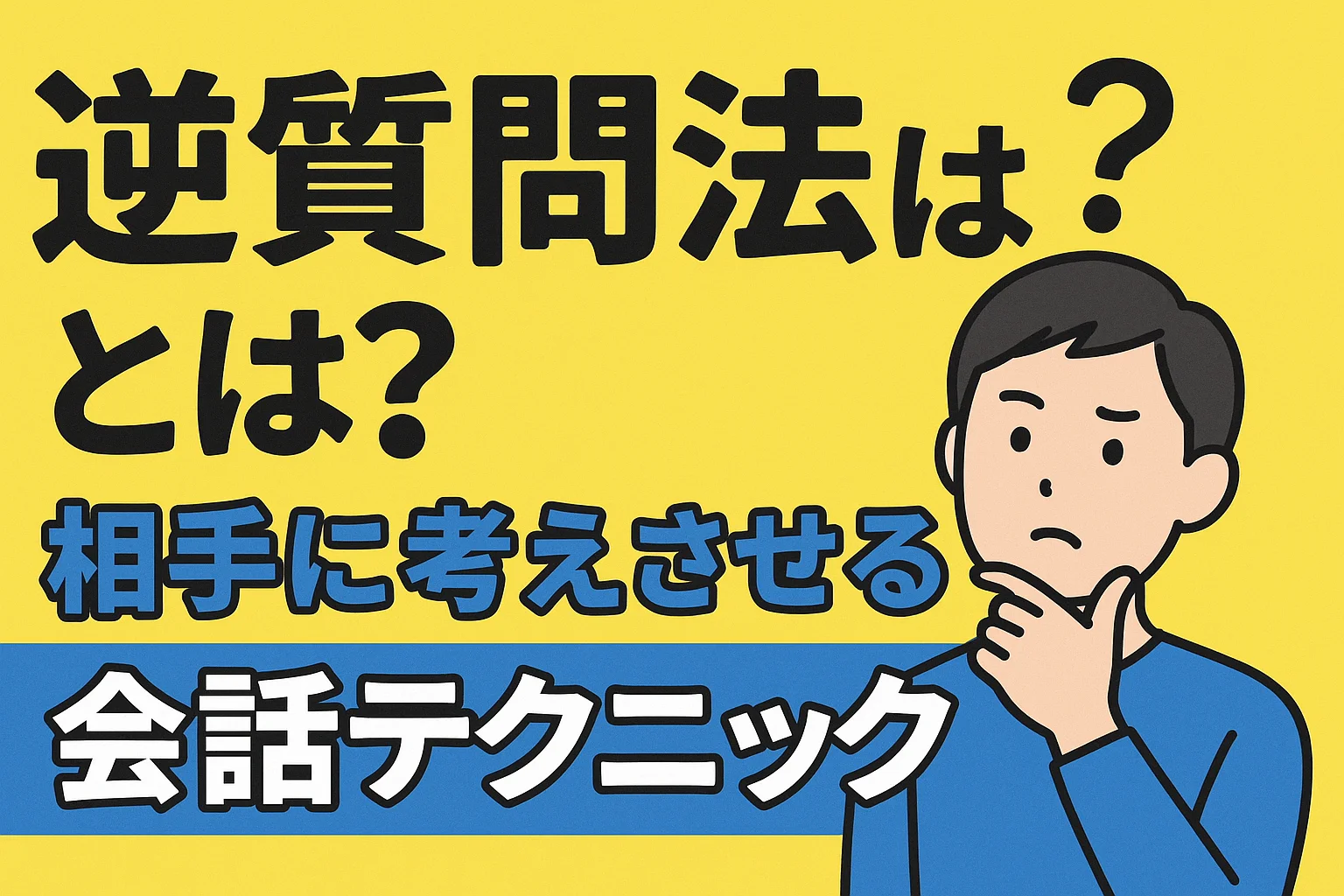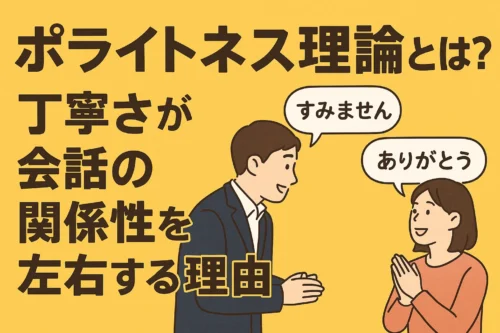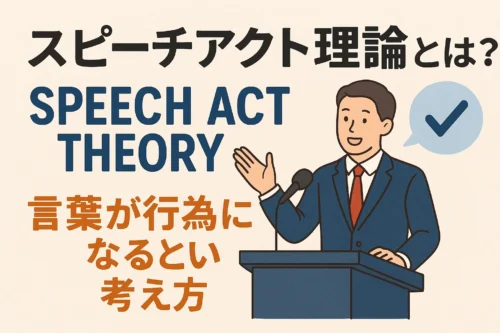毎日40人・年間1万人以上と会話しているRyoです。薬局のカウンターで質問責めにすると、相手がだんだん黙り込むことがあります。そんなとき役立つのが「逆質問法」。こちらが質問を返すことで、相手自身に考えてもらうテクニックです。面倒に見えて、実は信頼関係を深める最強の方法だったりします。
こんな悩みありませんか
- こちらが話しすぎて相手の本音がわからない
- アドバイスしても相手が実行しない
- 会話が一方通行になりがち
昔の私は、患者さんの悩みを全部こちらで解決しようとして、逆に空回りしていました。逆質問法を取り入れてからは、相手が自分で答えを見つける場面が増え、会話がぐっと楽になりました。
逆質問法の基本
逆質問法とは
相手の質問に対して、こちらから質問を返すコミュニケーション技術です。「どうしたらいいですか?」と聞かれたら、「あなたはどうしたいと思います?」と問い返す。相手の思考を引き出し、主体性を促す狙いがあります。
効果が出る理由
人は自分で考えた答えほど実行しやすいもの。こちらが正解を押し付けるより、相手自身が考えたほうが納得感があります。また、逆質問は相手の内省を促すため、会話が深まりやすくなります。
逆質問法の使い方
基本の流れ
- 相手の話を最後まで聞く
- 要点をまとめて返す(リフレクション)
- 「あなたはどう思いますか?」と質問を投げる
- 相手の答えを受け止め、必要ならサポートを提案
この流れを意識するだけで、相手が自分事として考え始めます。
具体的なフレーズ例
- 「それって、どんな選択肢がありそうですか?」
- 「一番困るのはどんなところです?」
- 「もし理想の形にできるとしたら、どうしたいですか?」
現場での実践例
調剤カウンターでのエピソード
ある患者さんに「飲み忘れが続いてて困る」と言われたとき、以前なら「アラームかけましょう」と即答していました。でも今は「どんなタイミングで忘れやすいですか?」と質問を返す。すると「夜は子どもの世話でバタバタして…」と背景が見えてくる。そこから「じゃあ夕食後すぐ飲む習慣にしてみましょうか」と本人のアイデアとして提案できました。
仕事の場面でも
部下に「この案件どう進めればいいですか?」と聞かれたとき、「君ならどう進める?」と返してみる。最初は戸惑うけれど、自分で案を出したほうが責任感が生まれるんですよね。私も新人のころ上司に同じことをされて、面倒くさいと思いつつ成長したなと感じています。
注意点
逆質問法は万能ではありません。相手が極度に疲れていたり、時間がないときに多用するとイライラされます。また、質問の返し方次第では「逃げている」と受け取られることも。ポイントは、相手の状況を見ながら適度に使うことです。「今はどうしたいか考えられそうですか?」と前置きしてから返すと、角が立ちません。
スキルを磨く練習方法
日常会話で試す
家族や友人との会話で、軽めの逆質問を試してみてください。「夕飯どうする?」と聞かれたら、「あなたは何が食べたい?」と返すだけでもOK。小さな練習が本番に効いてきます。
ロールプレイ
職場の勉強会などでロールプレイをすると、質問の投げ方を客観的に学べます。私の職場では、1人が相談役、もう1人が逆質問役を交代で行い、答えを導くプロセスを体感しています。
よくある失敗と対処法
- 質問が堅すぎる: いきなり「あなたのビジョンは?」とか聞くと引かれます。まずは日常的な言葉で。
- 答えを急かす: 沈黙が怖くてすぐにヒントを出してしまうと効果半減。相手が考える時間を尊重しましょう。
- 自分の意見を押し付ける: 逆質問後に「でもこうしたほうがいい」とすぐ言ってしまうのはNG。相手の案をまず肯定する姿勢が大事です。
応用編: 逆質問とメタモデルの併用
逆質問だけだと抽象的な答えで終わることもあります。そこでメタモデル質問を組み合わせると、相手の答えを具体化できます。「それを実現するには、どんな一歩が必要ですか?」と掘り下げる感じ。これで会話が一気に行動レベルまで落ちてきます。
練習を続けるコツ
毎日の会話で1回は逆質問を入れると決めておくと、自然と身についていきます。私はスマホのリマインダーに「今日の逆質問」と入れて、達成したらチェックをつけています。地味ですが、継続は力なりです。
まとめ
逆質問法は、相手に考えさせることで主体性を引き出す会話テクニックです。こちらが正解を用意する必要がないので、実はラク。相手も自分で答えを出すから納得して動きやすい。薬局の現場でも家庭でも、ちょっとした場面で使うだけで会話が深まり、信頼関係が育ちます。明日の会話で一つだけでも逆質問を投げてみませんか?きっと新しい発見があります。
ケーススタディ
家庭での逆質問
子どもが「宿題やりたくない」と言ったとき、「どうしたらやる気になると思う?」と聞き返してみる。すると「ゲーム終わってからならやる」とか、「一緒にやってくれる?」といった提案が出てきます。こちらが押し付けるより、ずっとスムーズに動いてくれるんですよね。
職場のミーティング
会議で沈黙が続くとき、私は「皆さんはどう考えてます?」と逆質問を投げます。誰かが話し出すと、他の人も意見を出しやすくなる。指名するよりも柔らかく参加を促せるので、会議の雰囲気が明るくなります。
よくある質問
Q1: 逆質問がわざとらしく感じられることは?
A1: あります。そんなときは自分の感想を一言添えてから質問すると自然になります。「僕はこう思うけど、あなたはどう感じます?」という感じです。
Q2: 相手が考えてくれないときは?
A2: 無理に答えを引き出そうとせず、「じゃあ少し時間を置いて考えてみましょうか」と締めるのも手。後日改めて聞くと、意外と考えてくれていたりします。
継続のヒント
- 1日1回、逆質問をする場面をメモして振り返る
- オープンクエスチョンを意識して語尾を柔らかくする
- 相手の表情を観察し、考えているときは黙って待つ
まとめの前に
逆質問法は、質問を返すだけでなく、相手を尊重する姿勢そのものです。答えを急がせず、相手のペースを待つのは面倒に感じますが、その余裕が信頼を生むと痛感しています。