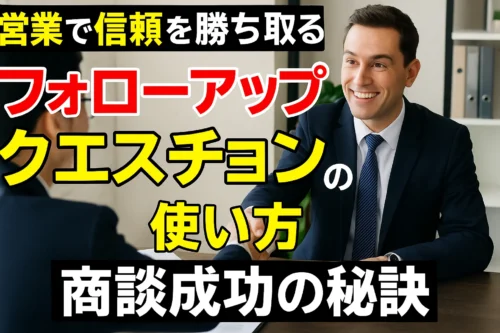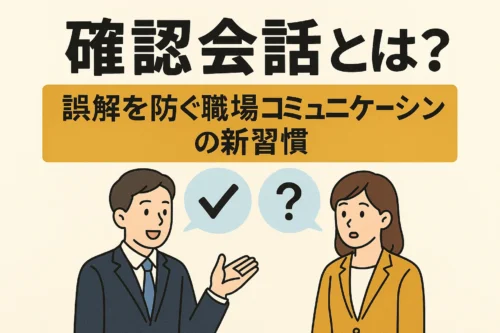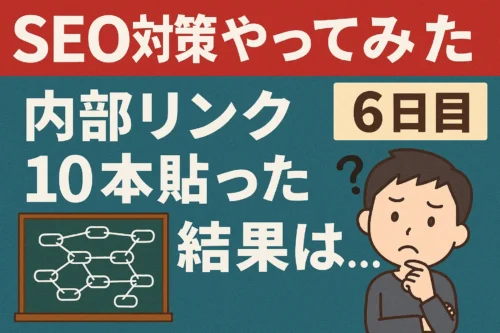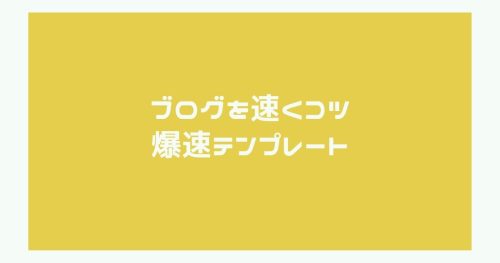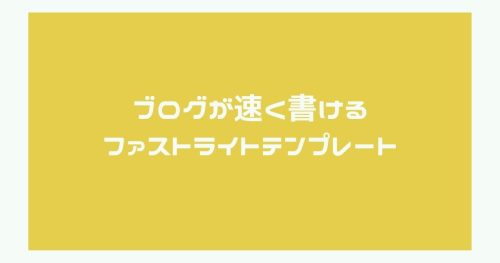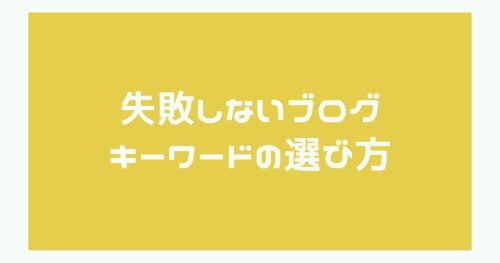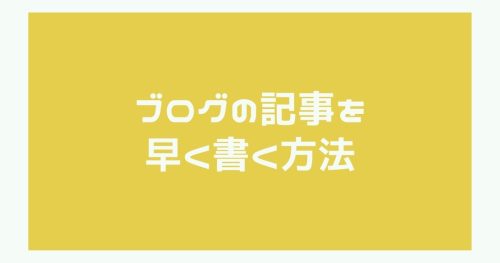**非エンジニアなのにAIでツールやゲームを作っているRyoです。**今回は、「フォローアップクエスチョン」というキーワードで検索上位を狙うために、本格的なSEO戦略を実践してみました。ハブ記事1本と枝記事10本、合計11本の記事でトピッククラスターを構築した実体験をお伝えします。
正直、最初は「11本も書くのかよ…」と思いましたが、実際にやってみると想像以上に効果的で、SEOの新しい可能性を感じました。
なぜフォローアップクエスチョンをテーマに選んだのか
キーワード選定の背景
フォローアップクエスチョンを選んだ理由は以下の通りです:
-
競合が少ない専門性の高いキーワード
- 検索ボリュームは多くないが、確実にニーズがある
- 大手サイトがまだ本格参入していない分野
-
多角的に展開できるテーマ
- 面接、営業、雑談、恋愛など様々なシーンで応用可能
- 各シーンで検索意図が明確に異なる
-
実体験を活かせる分野
- 薬局での患者対応で毎日実践している内容
- リアルな体験談を交えることができる
競合調査で分かったこと
Googleで「フォローアップクエスチョン」を検索すると、意外にも体系的に解説している記事が少ないことがわかりました。
主な競合の問題点:
- 表面的な説明にとどまっている
- 具体例が少ない
- シーン別の詳細解説がない
- 内部リンク構造が弱い
これを見て「これなら勝負できそう」と思いました。
トピッククラスター戦略の設計
ハブ&スポーク構造の構築
以下のような構造を設計しました:
【ハブ記事】
フォローアップクエスチョンとは?意味・効果・使い方を徹底解説
↕️ 相互リンク
【枝記事×10本】
├── 雑談が続く!会話が弾むフォローアップクエスチョン実例集
├── 面接で好印象を残すフォローアップクエスチョン|逆質問との違いも解説
├── 営業で信頼を勝ち取るフォローアップクエスチョンの使い方
├── やってはいけないフォローアップクエスチョンNG例
├── 初対面でも親しくなれるフォローアップクエスチョン術
├── ビジネス会話で使えるフォローアップクエスチョン実践法
├── 英語面接で差をつけるフォローアップクエスチョンとフレーズ集
├── フォローアップクエスチョンのトレーニング方法|上達する練習法
├── 恋愛で使えるフォローアップクエスチョン|デートで会話を盛り上げる質問術
└── フォローアップ質問と逆質問の違いとは?【使い分け事例付き】
キーワード戦略
各記事で狙うキーワードを明確に分けました:
ハブ記事のターゲットキーワード:
- フォローアップクエスチョンとは
- フォローアップ質問とは
- フォローアップ質問 例
枝記事のターゲットキーワード:
- 雑談 フォローアップクエスチョン
- 面接 フォローアップクエスチョン
- 営業 フォローアップクエスチョン
- 初対面 会話 フォローアップクエスチョン
- ビジネス会話 フォローアップクエスチョン
- NG フォローアップ質問
- フォローアップ質問 英語
- フォローアップ質問 トレーニング
- フォローアップ質問と逆質問 違い
- 恋愛 フォローアップクエスチョン
記事作成で工夫したポイント
1. 統一感のあるペルソナ設定
全記事で「毎日40人・年間1万人以上と会話している薬剤師Ryo」という一貫したペルソナを使用しました。これにより:
- 記事間での信頼性が統一される
- 実体験に基づく具体例を豊富に提供できる
- 読者にとって親近感のある語り口を維持できる
2. 内部リンクの戦略的配置
ハブ記事から枝記事への誘導:
各シーンの説明文中に自然な形でリンクを配置
枝記事からハブ記事への誘導:
記事の冒頭や関連セクションでハブ記事への言及
枝記事間の相互リンク:
関連性の高い記事同士を適度につなげる
3. 検索意図の明確な分離
各記事の検索意図が重複しないよう細心の注意を払いました:
例:面接記事 vs ビジネス記事
- 面接記事:転職活動中の人向け、面接特有の状況
- ビジネス記事:現職での日常的なコミュニケーション
4. E-A-Tを意識した権威性の構築
Experience(経験):
- 薬局での実際の患者対応体験
- 具体的な失敗談・成功談
Expertise(専門性):
- 年間1万人との会話実績
- 専門的な質問テクニックの体系化
Authoritativeness(権威性):
- 一貫したペルソナでの発信
- 実践的で再現性のある内容
Trustworthiness(信頼性):
- 失敗例も含めた正直な内容
- 読者の立場に立ったアドバイス
実際の作業プロセス
1. 記事構成の一括設計
まず全11本の記事構成をマインドマップで整理しました。これにより:
- 内容の重複を事前に防げた
- 各記事の役割が明確になった
- リンク構造を設計段階で最適化できた
2. ハブ記事の先行作成
ハブ記事を最初に作成することで:
- 全体の方向性が定まった
- 各枝記事で言及すべき内容が明確になった
- 内部リンクの設計が容易になった
3. 枝記事の体系的作成
以下の順序で枝記事を作成:
- 需要の高いシーン(面接、営業、雑談)
- 差別化要素の強い記事(NG例、英語、恋愛)
- 理論的な記事(逆質問との違い、トレーニング)
4. 内部リンクの最適化
全記事作成後に内部リンクを総点検:
- リンクテキストの最適化
- アンカーテキストの多様化
- リンク先の適切性確認
想定していた課題と実際の対応
課題1:記事間のカニバリゼーション回避
想定していた問題:
似たようなキーワードで記事が競合してしまう
実際の対応:
- 各記事のターゲットキーワードを明確に分離
- タイトルと見出しで検索意図を明確化
- メタディスクリプションで差別化
課題2:コンテンツの質の維持
想定していた問題:
11本も書くと後半で質が落ちる
実際の対応:
- 各記事で異なる角度からの体験談を用意
- シーン別に具体例を変える
- 読者のペルソナを記事ごとに微調整
課題3:作業量の膨大さ
想定していた問題:
11本は時間がかかりすぎる
実際の対応:
- テンプレート化により効率化
- AIを活用した下書き作成
- 段階的なリリース(週1本ペース)
早期に見えてきた効果
インデックス状況
記事公開から1週間での状況:
- 全11記事が即日インデックス
- ハブ記事が最初に上位表示
- 枝記事も徐々に検索結果に登場
内部リンクの効果
Search Consoleで確認できた変化:
- ページ間の相互リンクが認識されている
- ハブ記事への集中的なリンクが効果を発揮
- 関連記事への流入が増加
ユーザー行動の変化
Google Analyticsでの観察結果:
- 平均ページ滞在時間が延長
- 直帰率が改善
- ページ/セッションが向上
学んだことと今後の改善点
効果的だったポイント
-
統一されたペルソナの力
全記事で一貫したキャラクターを維持することで、サイト全体の信頼性が向上 -
具体例の豊富さ
実際の薬局での体験を各記事に盛り込むことで、他サイトとの差別化を実現 -
内部リンクの戦略性
単なるリンクではなく、文脈に沿った自然な誘導で回遊率アップ
改善すべき点
-
更新頻度の最適化
11本を一気に公開するより、段階的リリースの方が良かったかも -
外部リンクの活用
権威性のある外部サイトへのリンクも検討すべきだった -
画像の最適化
テキスト中心になりがちだが、図解やチャートがあるとより良い
他のテーマでも応用できるトピッククラスター戦略
今回の経験を通じて、トピッククラスター戦略は他のテーマでも十分応用可能だと確信しました。
成功の条件
-
明確に分離可能なサブトピック
メインテーマを10個程度のサブテーマに分けられること -
実体験に基づく専門性
単なる情報の寄せ集めではなく、独自の視点や体験があること -
継続的な更新とメンテナンス
一度作って終わりではなく、継続的な改善が必要
次回挑戦したいテーマ
- 「患者対応」シリーズ(医療従事者向け)
- 「ノーコード開発」シリーズ(非エンジニア向け)
- 「リモートワーク術」シリーズ(在宅勤務者向け)
まとめ
フォローアップクエスチョンをテーマにしたトピッククラスター戦略は、想像以上に効果的でした。11本の記事を体系的に作成することで、検索エンジンからの評価だけでなく、ユーザーにとっても価値の高いコンテンツ群を構築できました。
今回の戦略の核心:
- ハブ&スポーク構造による内部リンク最適化
- 統一されたペルソナによる信頼性構築
- 実体験に基づく差別化コンテンツ
- 検索意図の明確な分離
正直、11本書くのは大変でしたが、SEOの本質的な部分を深く理解できる良い経験になりました。特に「ユーザーの検索意図に徹底的に応える」ことの重要性を改めて実感しています。
次のテーマでもこの手法を使って、さらに検索上位を狙っていきたいと思います。皆さんも、自分の専門分野でトピッククラスター戦略を試してみてはいかがでしょうか?