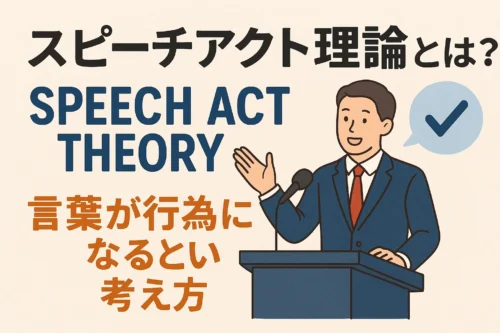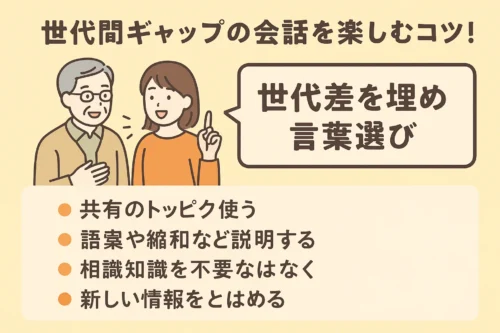毎日40人・年間1万人以上と会話しているRyoです。自分の声って案外コントロールしづらいですよね。気を抜くと早口になったり、疲れていると声が低くなったり。今日は、声の高さが相手にどんな印象を与えるのか、薬局での経験も交えながらお話しします。
こんな悩みありませんか?
「電話だと冷たく聞こえる」とか「初対面のとき緊張で声が裏返る」とか、声にまつわる悩みは誰しもあるはず。私も昔、説明に夢中になって声がどんどん高くなり、患者さんから「早口で聞き取りにくい」と言われたことがある。声の高さって意外と印象を左右するんですよね。
声の高さがもたらす心理効果
高い声が与えるイメージ
高い声は明るさや若さを連想させる一方で、落ち着きがないと感じる人もいる。特に年配の患者さんは、落ち着いた声を好む傾向があるので、あまりピッチを上げすぎると「頼りない」と思われがちです。ただし、受付や明るい接客の場では、程よい高さの声が場を和ませる。状況に応じた切り替えが大切ですね。
低い声が与えるイメージ
低い声は安心感や信頼感を与えやすい。ただ、低すぎてぼそぼそ話すと聞き返される回数が増える。私は花粉症で鼻が詰まると声がガラガラになるんですが、そのときに無理に低く話すと余計聞き取りづらくなる。低い声=良い、ではなく、響きやすい声を意識するのがポイントです。
ピッチの変化が感情を伝える
声は感情のバロメーター。喜びや驚きを伝えるときは自然に高くなり、落ち着いて説明するときは低くなる。この変化があることで、相手は「話に抑揚がある」と感じ、飽きずに聞いてくれる。ずっと同じ高さで話していると機械みたいで、人間味がないって言われちゃうかもしれません。
声の高さをコントロールするコツ
呼吸を整える
高すぎる声は、呼吸が浅くなると出やすい。私は忙しい日ほど肺がペラペラになって、高めの声が連発する。深呼吸を意識すると声が落ち着くし、話すスピードも自然にゆっくりになる。会話中に一息置くのは、相手に考える時間を与える意味でも有効です。
発声練習で響きを作る
声帯のストレッチなんて面倒だと思っていたけど、5分くらい「あーえーいーおーうー」を繰り返すだけでもかなり違う。特に低音をしっかり出す練習は、声に厚みを出してくれる。薬局の開店前にこっそりやると、朝一番の患者さんにも落ち着いた声で対応できるようになります。
相手に合わせて高さを微調整
コミュニケーションはキャッチボール。相手がゆっくり低い声で話しているなら、こちらも少しトーンを下げる。逆にテンション高めの人には、少しだけピッチを上げる。大げさな真似は不要だけど、相手のリズムを意識すると会話のテンポが合いやすいです。
現場での実践例と注意点
受付での第一声
朝一番、眠そうな患者さんが来たときに高い声で「おはようございます!」と叫ぶと、たまにビクッとされる。そんなときは声の高さを半音下げて、少し柔らかく「おはようございます」と言うだけで反応が変わる。相手の状態を観察してから声を出すと、空気が整います。
電話応対のコツ
電話だと表情が見えない分、声の高さが印象を決める。私は最初にほんの少し高めの声で名乗り、その後は落ち着いたトーンに戻すようにしている。これで相手に明るさと安心感の両方を伝えられる。つい早口になるときは、話しながらメモを取るとテンポが落ち着くのでおすすめです。
まとめ
声の高さは、自分では気づきにくいけれど相手に大きく影響します。高すぎても低すぎてもダメで、状況と相手に合わせて柔軟に調整するのが理想。面倒ですが、ちょっと気を配るだけで信頼度がぐっと上がります。今日から自分の声を録音して聞き返してみませんか?客観的に知ることが、改善への近道です。