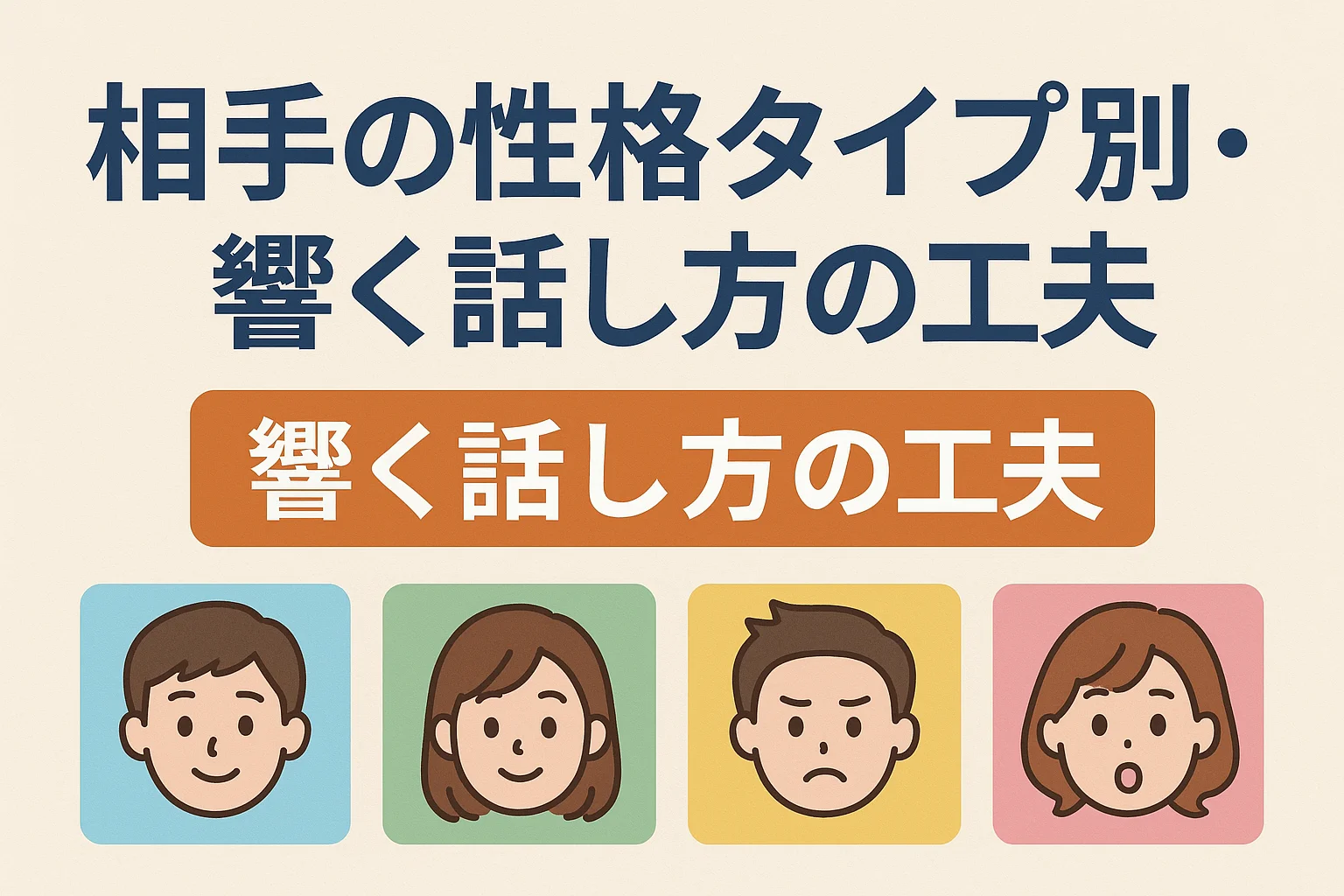毎日40人・年間1万人以上と会話しているRyoです。同じ薬の説明をしても、患者さんによって反応が全然違うんですよね。
「データを詳しく知りたい」人もいれば、「簡潔に要点だけ」って人もいる。性格タイプに合わせて話し方を変えるだけで、患者さんの理解度と満足度が劇的に変わります。
今日は年間1万人との接客でわかった、性格タイプ別の効果的な話し方をお話しします。
4つの基本性格タイプ
1. 論理思考タイプ(データ重視)
特徴:
- 根拠やデータを求める
- 詳細な説明を好む
- 質問が多い
- 慎重に判断する
話し方のコツ:
- 具体的な数値を伝える
- 「なぜなら」で理由を説明
- 資料やデータを活用
- 時間をかけて丁寧に
実例:
「この薬は臨床試験で78%の方に効果が認められました。副作用は100人中3人程度で、主に軽い眠気です。血中濃度が安定するまで約1週間かかりますので、効果の判定は1週間後になります」
2. 感情重視タイプ(共感優先)
特徴:
- 人との関係を大切にする
- 感情的な安心感を求める
- 体験談や事例を好む
- 薬剤師との信頼関係を重視
話し方のコツ:
- 共感の言葉を多く使う
- 実際の患者さんの例を紹介
- 安心感を与える表現
- 温かいトーンで話す
実例:
「同じお薬を使ってる患者さんからは『楽になった』というお声をたくさんいただいてます。最初は不安に思われるかもしれませんが、私たちがしっかりサポートしますので安心してくださいね」
3. 行動重視タイプ(結果優先)
特徴:
- 結論を早く知りたがる
- 簡潔な説明を好む
- 効率を重視
- 時間を大切にする
話し方のコツ:
- 結論から先に伝える
- 要点を3つに絞る
- 手順を明確に
- テキパキと説明
実例:
「結論から申し上げます。この薬で症状は改善します。飲み方は朝食後に1錠、2週間続けてください。効果は3日程度で実感できるはずです」
4. 安定重視タイプ(リスク回避)
特徴:
- 変化を嫌う
- 安全性を最重視
- 慎重で心配性
- 確実性を求める
話し方のコツ:
- 安全性を強調
- リスクと対策を説明
- 段階的に説明
- 繰り返し確認
実例:
「この薬は長年使われている安全なお薬です。万が一体調に変化があった場合は、すぐに連絡してください。私たちが24時間サポート体制を整えています。何か心配なことがあれば、遠慮なくお聞かせください」
タイプの見分け方
質問の仕方でわかる
論理思考タイプ:
「この薬の成分は何ですか?」
「副作用の発現率はどのくらいですか?」
感情重視タイプ:
「他の人はどう言ってますか?」
「先生は信頼できますか?」
行動重視タイプ:
「いつから効きますか?」
「簡単に教えてください」
安定重視タイプ:
「副作用は大丈夫ですか?」
「前の薬と比べてどうですか?」
表情や態度でわかる
論理思考タイプ:
- メモを取る
- 真剣な表情
- 質問が多い
感情重視タイプ:
- 表情豊か
- うなずきが多い
- 薬剤師の顔をよく見る
行動重視タイプ:
- 時計を見る
- 早口で話す
- 要点を求める
安定重視タイプ:
- 心配そうな表情
- 何度も確認
- 慎重な口調
実際の対応例
血圧の薬を初めて飲む60代男性(論理思考タイプ)
「この薬はACE阻害薬という種類で、血管を拡張して血圧を下げます。臨床データでは平均して収縮期血圧が15-20mmHg下がります。副作用として空咳が5-10%の方に見られますが、薬を中止すれば改善します。効果判定は2-4週間後に行います」
同じ薬を同じ患者さん(感情重視タイプ)に説明
「血圧のお薬ですね。多くの患者さんが『体が楽になった』とおっしゃってます。最初は新しい薬に不安もあると思いますが、私たちがしっかりサポートしますので安心してください。何か気になることがあれば、いつでも相談してくださいね」
混合タイプへの対応
実際の患者さんは、複数のタイプが混在していることが多いです。
対応のコツ:
- 最初は様子を見る
- 相手の反応に合わせて調整
- 複数のアプローチを組み合わせる
例:
「血圧を下げる安全なお薬です(安定重視)。効果は2週間程度で実感できます(行動重視)。多くの患者さんに喜んでいただいてます(感情重視)。臨床試験でも高い効果が証明されています(論理思考)」
タイプ別NGワード
論理思考タイプに言ってはいけない
- 「とりあえず飲んでください」
- 「詳しいことはわかりません」
- 「心配いりません」(根拠なし)
感情重視タイプに言ってはいけない
- 「データ的には…」(冷たく感じる)
- 「理論的に考えて…」
- 「客観的に判断すると…」
行動重視タイプに言ってはいけない
- 「詳しく説明すると…」
- 「時間をかけて…」
- 「ゆっくり考えて…」
安定重視タイプに言ってはいけない
- 「新しい薬です」
- 「試してみましょう」
- 「大丈夫です」(根拠なし)
まとめ:一人ひとりに合わせたコミュニケーション
性格タイプを理解することで、患者さん一人ひとりに最適な説明ができます。
ポイントまとめ:
- 4つの基本タイプを理解
- 質問や態度でタイプを見分ける
- それぞれに適した話し方を選択
- 混合タイプには柔軟に対応
- NGワードを避ける
同じ薬の説明でも、相手に合わせて伝え方を変えるだけで、理解度と信頼関係が大きく変わります。
私も最初は「薬の説明は1つのパターンでいい」って思ってました。でも患者さんのタイプに合わせて話すようになってから、「わかりやすい」「安心した」って言ってもらえることが増えました。
明日からの接客で、患者さんのタイプを意識してみてください。きっとコミュニケーションの質が向上しますよ!