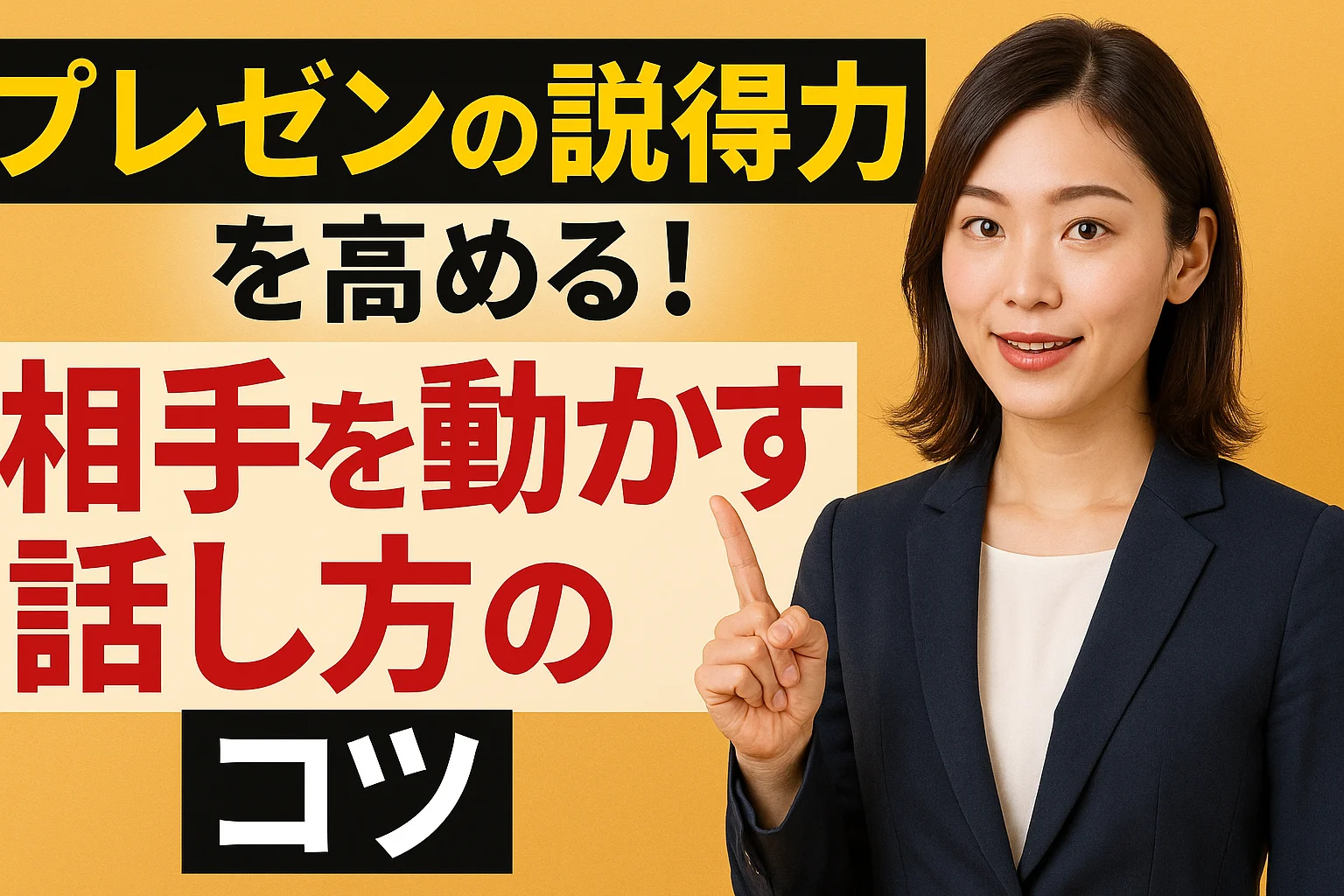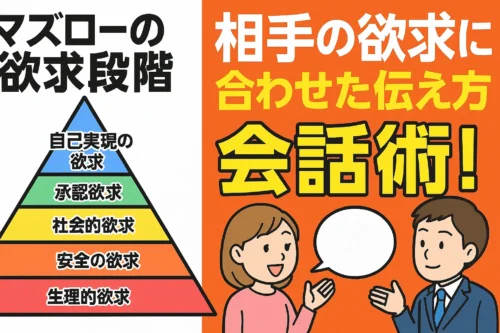毎日40人・年間1万人以上と会話しているRyoです。薬局のカウンターで患者さんに薬を説明するのも、社内で資料を共有するのも、結局はプレゼン。目の前の相手にわかりやすく伝えつつ、こちらの意図を汲んでもらえるかどうかで、その後の行動が変わります。仕事が忙しくて準備に時間をかけられない人ほど、話し方の型を身につけておくとラクになるので、今日はプレゼンで相手を動かすためのコツをまとめます。
読者の悩みを整理する
伝えているのに動いてくれない
プレゼンで時間をかけて説明したのに、聞き手がいまいちピンと来ていない顔をしている。そんな経験、誰でも一度はあるはずです。薬局でも「この薬は1日3回飲んでください」と繰り返し伝えても、家に帰ったら忘れたという患者さんが少なくありません。伝えたはずなのに相手の行動が変わらないと、正直へこみますよね。
資料づくりに振り回されて本質が抜ける
見映えのいいスライドを作ることに時間を取られ、肝心のメッセージがぼやけてしまうこともあります。僕も新人のころは、アイコンやアニメーションに気を取られて、伝えたいポイントを忘れることがよくありました。これでは相手の頭に残るはずがありません。
緊張して言葉が詰まる
人前に立つとどうしても緊張するものです。僕も初めて薬局長に企画を提案したとき、喉がカラカラになって思うようにしゃべれませんでした。話がうまくまとまらないと、説得力も半減してしまいます。
原因を理解する
自分視点で話してしまう
プレゼンがうまく伝わらない原因の一つは、自分の言いたいことだけを中心に組み立ててしまうこと。僕も最初は「この新しいジェネリックを推したい」という思いが強すぎて、患者さんの立場を忘れていました。相手が求めている情報やメリットを把握しないまま話すと、どうしても独りよがりになってしまいます。
情報の順番がバラバラ
重要なポイントが散らばっていると、聞き手は途中で迷子になります。結論がどこにあるのかわからず、聞き手の集中力が切れてしまうのです。薬の服用指導でも、最初に効能ばかり並べると、患者さんは肝心の飲み方を聞き逃すことがあります。
視覚と聴覚が一致していない
話す内容とスライドの情報が一致していないと、聞き手はどちらに注意を向けるべきか迷ってしまいます。薬の説明でも、添付文書と口頭での説明がバラバラだと、患者さんは不安になります。視覚と聴覚を揃えることは、説得力を高める基本です。
解決手順
相手の現状とゴールを最初に共有する
プレゼンの冒頭で「現状」「課題」「目指すゴール」をセットで示すと、聞き手の頭の中に地図ができます。薬局なら「現在この薬を使っていて副作用が出ている→ジェネリックを使えば改善する」という流れを最初に提示します。これだけで聞き手の集中度が変わります。
結論ファーストで全体像を見せる
先に結論を言い切ると、聞き手は安心して詳細を聞けます。僕がプレゼンをするときは、「結論から申し上げますと、この新しい服薬指導アプリを導入すると、患者さんの飲み忘れが3割減ります」と冒頭で伝えます。そのあとに根拠や具体例を示すと、説得力がぐんと増します。
ストーリーラインを組み立てる
- 課題の明確化
- 解決策の提示
- 期待できる効果
- 実行ステップ
この順番で話すと、聞き手の理解が自然と深まります。薬局で患者さんの服薬アドヒアランスを上げたいときも、課題を共有し、解決策としての声かけ方法を提案し、実際の効果を示す、と段階的に話すようにしています。
聴覚と視覚の同期
スライドはシンプルにまとめ、話す内容と一致させます。文字だらけのスライドは見ただけで疲れますから、キーワードだけを載せて、口頭で補足するスタイルが良いです。薬の説明書を読み上げるだけでは患者さんは理解できませんが、図や表を使いながら簡潔に説明すると、飲み方を覚えやすくなります。
間を恐れず、視線を合わせる
緊張すると早口になりがちですが、あえて間を取ることで聞き手の理解を促せます。薬局でも患者さんが質問を考える時間を作るため、あえて数秒黙ることがあります。視線を合わせることで、こちらの真剣さも伝わります。
体験談を交える
実際のエピソードは説得力を倍増させます。「このジェネリックに変えた患者さんが、『飲みやすくなったから続けられた』と言ってくれた」と紹介すると、聞き手は具体的なイメージを持ちやすくなります。プレゼンでも「前回この方法で採用が決まりました」という体験談を入れるだけで印象が大きく変わります。
実践例と注意点
実践例: 少人数ミーティングでのプレゼン
社内の少人数ミーティングで新しい薬品管理システムを導入する提案をしたとき、僕は次の手順を踏みました。まず、現状の課題として「在庫管理がアナログでミスが多い」を示し、導入後のゴールとして「在庫の視認性が上がり、廃棄ロスが減る」を提示。結論を先に述べ、導入手順をステップに分けて説明しました。実際に導入した後、棚卸しにかかる時間が半分になり、説得力があったと評価されました。
実践例: 患者さんへの服薬指導
高血圧の患者さんに新しい薬を提案する際も、「今の薬では副作用が出ている」という課題と、「この薬なら副作用が少ない」という解決策を明確に伝えました。飲み始める前と後の血圧の変化をグラフで見せることで、視覚的な説得力が増しました。
注意点: 情報を詰め込みすぎない
熱が入るとつい情報を盛り込みたくなりますが、聞き手が処理できる量には限りがあります。薬の副作用をすべて列挙するより、起こりやすいものだけを伝えた方が記憶に残ります。プレゼンでも、ポイントは3つ程度に絞るのが無難です。
注意点: 相手のリアクションを無視しない
聞き手が首をかしげたり、メモを取らなくなったりしたら、理解が追いついていないサインです。薬局でも、患者さんが眉をひそめたら説明の仕方を変えるようにしています。プレゼンでも同じで、相手の反応を見ながらスピードや言葉を調整することが大切です。
まとめ
プレゼンの説得力を高めるには、相手の視点を理解し、結論ファーストでシンプルに伝えることがポイントです。ストーリーラインを意識し、視覚と聴覚を揃えながら体験談を交えると、相手は自然と動きたくなります。僕自身、薬局でのコミュニケーションを通じてこのスタイルを身につけてきました。何度もプレゼンを繰り返していくと、自分なりの言葉が磨かれていきます。面倒でも型を持っておくと、どんな場面でも自信を持って話せるようになりますよ。