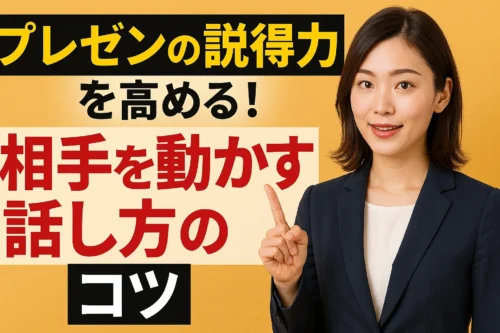毎日40人・年間1万人以上と会話しているRyoです。今日も現場で薬を渡しながら、どう交渉すれば相手が納得するか悩む人の相談を受けました。
ドア・イン・ザ・フェイスって聞いたことありますか?一度断られてから本命の提案を通す、あの心理術です。
面倒くさそうに見えるかもしれませんが、上手く使えばマジで交渉が楽になります。
読者の悩み:お願いしても相手が動いてくれない
患者さんに追加の検査をお願いすると「忙しいから今度にして」とかわされる。営業先に見積もりの再検討を頼んでも「予算がない」と即答される。そんな場面、現場では毎日のようにあります。こちらが真剣に伝えても、相手は面倒を感じたり損をしたくなかったりで動いてくれない。この繰り返し、正直しんどいですよね。
何度頼んでも断られる理由
人は最初に提示された要求の大きさで構え方を決めます。最初のお願いが重いと感じれば、その後の話は聞いてくれません。「またか」と思われた瞬間、こちらの言葉は耳に入らない。僕も新人のころ何度も空振りしてきました。
ちょっとしたズルさが必要?
ズルいと感じるかもしれませんが、交渉には小さな仕掛けが必要です。相手の心理を読まずに真正面から行くと、疲れるだけで成果が出ない。ドア・イン・ザ・フェイスはその仕掛けの一つ。大きな要求をまず出して断らせることで、本命の小さな要求を通しやすくするんです。
原因解説:大きな要求が断られるメカニズム
人が「いやだな」と感じるラインはそれぞれですが、一般的に最初に示された基準がその後の判断に影響します。これを対比原理と言います。大きな要求を断った後に小さな要求を提示されると、相手は「これならまだマシか」と感じてしまう。この心理の揺らぎを上手く使うのがドア・イン・ザ・フェイスです。
対比原理と譲歩の印象
最初の要求を断った側は、どこか後ろめたさを抱えています。そこにこちらが譲歩したように見える提案をすると「断って悪かったな」という気持ちが働き、受け入れやすくなる。これは誰にでもある感情です。薬局のカウンターでも、強めの検査を提案して断られた後に「じゃあまずはこの簡単なチェックから」と言うと多くの方が頷いてくれます。
身近な場面での例
例えば、同僚に当直を頼みたいとき。いきなり「今月全部代わって」と言えば100%断られます。でもその後に「じゃあ土曜日の一回だけでもお願い」と続けると、さっき断った負い目もあり「それくらいなら」と応じてくれる人が多い。これがまさにドア・イン・ザ・フェイスの典型例です。
解決手順:ドア・イン・ザ・フェイスの使い方
実際に使うときは、適当に大きな要求を出せばいいわけではありません。相手の性格や状況に合わせて計算する必要があります。
準備する内容
- 本当に通したい本命の要求を明確にする。
- 相手が確実に断るであろう大きな要求を設定する。
- 断られた後にすぐ出すフォロー案を用意する。
準備を怠ると、ただの無礼な人になってしまうので注意です。
実際の流れ
まずは大きなお願いを真面目に伝えます。断られるのを恐れて尻込みすると、相手に「どうせ引っ込めるだろ」と読まれてしまう。断られたらすぐに「ではこちらはどうでしょう」と本命の要求を提示。この間をあけないのがポイント。間が空くと相手は交渉が終わったと思い、再度構え直してしまうからです。
断られた後のフォロー
本命の要求を出した後は、相手の返事を急かさず、こちらが譲歩したという空気を醸し出します。例えば「急にお願いしてすみません。これなら負担は少ないと思うんですがどうでしょう」と柔らかく言う。これだけで受け入れ率がかなり変わります。
実践例・注意点:現場で試したケース
薬局では患者さんとの信頼関係が命です。だからこそ、この手法を乱用すると逆効果になります。ここでは僕が現場で実際に使ってうまくいった例と、失敗した例も正直に紹介します。
薬局でのエピソード
ある高血圧の患者さんに24時間血圧計の装着を提案したときのこと。最初は「毎日通院してもらえませんか」と大きくお願いしました。もちろん「無理だよ」と即答されましたが、その直後に「では1週間だけ24時間計を付けてみませんか」と続けると、意外にも「それなら」と受け入れてくれました。後で聞いたら「最初のお願いを断った罪悪感があった」と笑っていました。
営業での応用
知人の営業マンは、法人契約を取る際にまず年間プランを提示し、断られたら月額プランを提示する方法で契約率を上げています。お客さんは最初に高額の年間プランを見せられることで「これは無理」と判断しますが、その後に月額プランを見せられると「思ったより安い」と感じる。数字のマジックとは恐ろしいものです。
やり過ぎへの注意
ただし、大きな要求が常識から外れすぎると相手を怒らせるだけ。例えば1万円の商品を売りたいのに最初に100万円を提示したら、ふざけていると思われます。相手が不快に感じるギリギリを見極めるのが腕の見せどころです。
心理学的背景:研究から見える効果
ドア・イン・ザ・フェイスは1970年代に社会心理学者のロバート・チャルディーニが実験で明らかにしたテクニックです。大きな要求を断った後に小さな要求を出すと承諾率が大幅に上がるという結果が何度も再現されています。
実験の概要
チャルディーニの代表的な実験では、学生に「少年更生施設で2年間ボランティアをしてくれないか」と尋ねました。当然ほとんどが断ります。そこで研究者はすかさず「では今週末の2時間だけ散歩に付き合ってくれないか」とお願いしました。すると驚くほど多くの学生が「それなら」と承諾したのです。
承諾の背景にある心理
人は一度断ると、どこかで「申し訳ない」と感じます。さらに、相手が大きな要求から小さな要求に切り替えることで「相手も譲歩した」と感じ、自分も歩み寄らなければと無意識に考えてしまう。これが交渉の場で強力に働きます。
練習方法と現場でのステップ
理屈はわかっても、いきなり本番で使うのは怖い。そこで、日常のささいな場面で練習するのがおすすめです。
日常会話でのトレーニング
例えば友人とのランチ。いきなり高級店を提案して断られたら、すぐに「じゃあ近くの定食屋にしよう」と続ける。これを繰り返すことで、断られた後の切り返しが自然にできるようになります。わざと大きな提案をするので、友人には事情を説明しておくとトラブルになりません。
現場でのステップ
- 目的を明確にし、通したい本命の要求を紙に書く。
- 相手が拒否するであろう大きな要求を考え、その理由も整理する。
- 実際の会話では落ち着いて大きな要求を伝え、断られたらすぐフォロー案を提示。
- 相手が迷っているときは、負担が減る具体的な数字や期間を提示して安心させる。
失敗したときのリカバリー
うまくいかないときは「言い過ぎました、気を悪くしないでください」と素直に謝る。ここで開き直ると信頼がガタ落ちします。誠実さを忘れなければ、多少の失敗は笑い話で終わります。
よくある質問
ここでは現場で後輩からよく聞かれる疑問に答えておきます。
Q1: 大きな要求はどれくらいオーバーにするべき?
相手が「冗談だろ」と笑う程度では効果が薄い。真剣に断られるラインを狙います。普段の会話から相手の許容範囲を観察しておくと、的確なラインが見えてきます。
Q2: 毎回この手法を使うと嫌われない?
乱用すると間違いなく嫌われます。ここぞという場面でのみ使い、普段は正攻法のコミュニケーションを心がけましょう。信頼関係があってこそ効果を発揮します。
Q3: 断られた後に沈黙が怖い
沈黙が怖いのはわかりますが、すぐに喋りすぎると相手に考える余地を与えません。深呼吸して3秒待つだけで印象が変わります。僕もこれが苦手で、今でも意識して練習しています。
まとめ
ドア・イン・ザ・フェイスは、相手の心理的な譲歩を引き出す強力なテクニックです。ただし使い方を間違えると信頼を失うリスクもある。最初に大きな要求を出し、本命の要求を通す。この流れを意識しながら、相手の立場や状況に寄り添って使ってください。現場で何度も試していると、どの程度の要求が適切か肌感覚でわかってきます。交渉で行き詰まったとき、選択肢の一つとして思い出してもらえれば嬉しいです。
明日から試そう
難しそうに見えて、慣れると日常会話にも応用できます。まずは身近な友人や同僚とのやりとりで練習し、自分なりの距離感を掴んでください。マジで世界が変わります。僕もまだまだ勉強中ですが、一緒に試行錯誤していきましょう。
参考になる一歩目
僕が最初にこの手法を学んだのは、研修で見たロールプレイでした。大きなお願いをして断られた後、静かに本命を出す先輩の姿が忘れられません。その滑らかな切り返しに「プロだな」と感動したものです。書店に並ぶ交渉術の本にも似たような事例が山ほど載っていますが、実際に口に出して練習しないと身につきません。ノートに台本を書き、声に出して読むだけでも効果があります。
失敗しても凹まない
失敗すると落ち込みますが、経験を積むと段々と勘が鋭くなります。相手の表情や沈黙の長さで、「次の一手を出すタイミング」がわかるようになる。僕も今でもときどき滑りますが、そこで諦めずに調整することで次に活かせます。継続がマジで力になります。