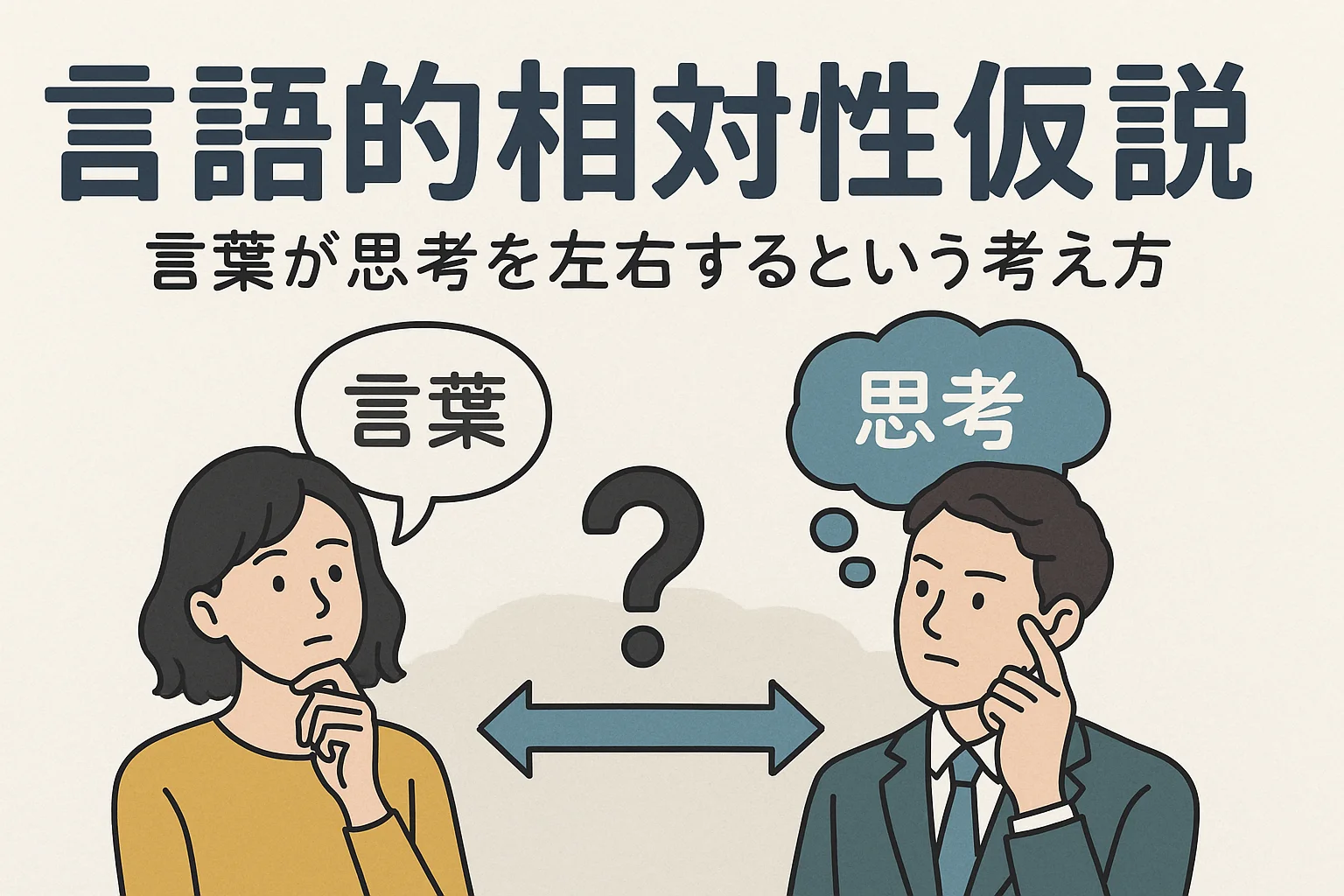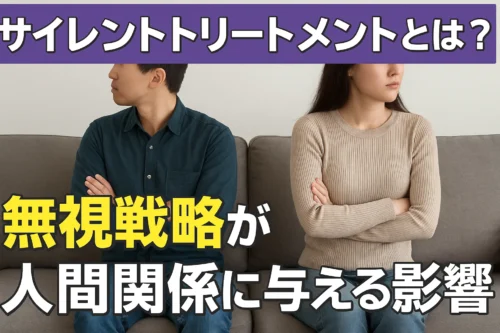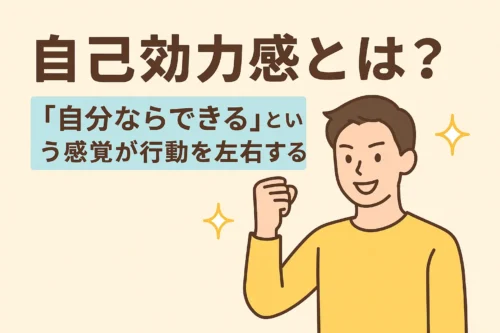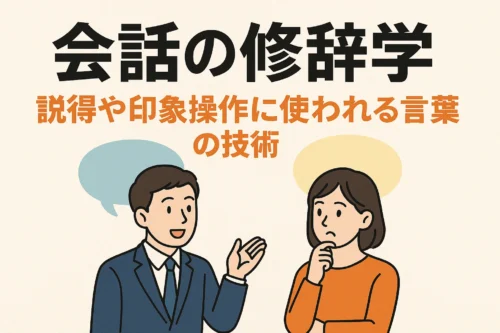毎日40人・年間1万人以上と会話しているRyoです。
「言葉が変われば世界の見え方が変わる」って、マジであるんですよ。薬局で患者さんと話していると、同じ薬でも言い方次第で反応が全然違います。今回はその背景にある「言語的相対性仮説」という考え方を、難しい専門用語を避けて紹介します。
言語的相対性仮説とは?
言語的相対性仮説は「人の思考や世界の捉え方は、使っている言語によって左右される」という考え方です。例えば青と緑を一つの言葉で表す言語では、青と緑の区別があいまいになることがあります。逆に、色に細かい名前が付いている文化の人は、微妙な色の違いを見分けるのが得意だったりします。
この仮説は昔から議論されていて、完全に正しいとも完全に間違いとも言い切れません。でも日常の会話の中でも「言葉の選び方で相手の理解が変わる」という実感は多くの人が持っているはずです。
思考が言葉によって影響を受ける仕組み
色の例
色の感じ方は言語によって差が出やすい分野です。私が以前海外旅行に行った時、英語で「blue」としか言わない場面でも、日本語では「空色」「藍色」「紺色」など細かい表現が可能です。反対に、海外の友人が「light blue」としか言えない時、なんだか物足りなく感じたのを覚えています。言葉のラベルがあるかどうかで、色の世界の豊かさが変わってしまうんです。
空間認識
言語によっては「右・左」ではなく「北・南」で方向を表す文化があります。そういう地域では、子どもでも常に自分がどちらを向いているか把握しているそうです。日本語ではそこまで厳密な表現をしないので、方向音痴になりやすい?なんて勝手に思ったりします。方向を示す言葉の違いが、空間の捉え方に影響を与えている良い例です。
薬局で感じた言語的相対性
医療用語とやさしい日本語
薬局では医療用語を使い慣れていても、患者さんには「難しそう」と受け取られることがあります。例えば「服薬」よりも「飲む」と言った方がすっと入る人も多いです。言葉を変えるだけで、患者さんの表情が明るくなるのを見ると、「言葉が思考を変える」って本当だなと実感します。専門用語が多いと相手は身構えてしまい、説明が頭に入っていかないこともよくあります。
方言と服薬指導
地域によって方言を使った方が伝わりやすい場面もあります。ある高齢の患者さんに標準語で説明してもいまいちピンと来ていない様子だったので、思い切ってその方の方言で「これ、寝る前にちゃんと飲んどきなはれ」と言ってみたら、すぐに理解してくれました。言葉が変わると、相手の心の扉が開く瞬間が見えるんです。
言葉を意識するメリット
誤解を防ぐ
言葉の選び方一つで誤解が生まれることも防げます。例えば「副作用があります」と言うと怖がる患者さんも、「体が慣れるまでに出る可能性があります」と言い換えると安心してくれたりする。言語的相対性仮説を知っていると、相手の思考がどう変わるかを意識でき、余計な不安を与えずに済みます。
相手の世界観を尊重する
相手の使っている言葉を尊重することで、その人がどんな世界観で生きているか理解しやすくなります。例えば、「しんどい」という言葉をよく使う人は、体調だけでなく気持ちの疲れも含めて伝えていることが多いです。こちらがその言葉を拾って話を広げると、「わかってくれた」と感じてもらえる。言葉はその人の世界観の一部なので、それを大事に扱うことがコミュニケーションの基本だと感じます。
まとめ
言語的相対性仮説は、日常の会話にも直結する実用的な考え方です。私たちが使う言葉は、単なる情報伝達の手段ではなく、思考や価値観そのものを形作っています。薬局での対話でも、言葉を少し意識するだけで相手の理解や安心感が大きく変わります。普段何気なく使っている言葉が、自分や相手の世界をどう作っているのか、ふと立ち止まって考えてみるとコミュニケーションがもっと楽しくなるはずです。
言葉選びを鍛える日々のトレーニング
読み慣れない表現に触れる
普段から本や記事を読み、知らない言葉に出会ったら意味を調べる癖をつけると、思考の幅も広がります。私は通勤時間にニュースアプリを眺め、難しい言い回しがあればメモしています。後で患者さんに説明する際、その表現をわかりやすく言い換える練習をすると、自然と語彙が増えていきます。
他言語を少し学んでみる
外国語を学ぶと、日本語にはない概念が見えてきます。英語で薬の説明書を読むと、「take with water」など直訳しにくい表現がたくさんあります。それを日本語でどう伝えるか考えるだけで、言語と思考の関係に気づかされます。別に完璧に話せなくても、別の言語に触れるだけで視野が広がるんです。
書き言葉と話し言葉を切り替える練習
文章を書くときは丁寧に、話すときはシンプルに。こうやって意識的に切り替えると、頭の中で二つの思考回路を持てるようになります。薬局でも「処方箋をお預かりします」と言う時と、書類に「処方箋受付」と書く時では、言葉の選び方が違いますよね。両方の表現を行き来することで、言語が思考をどう導いているか体感できます。