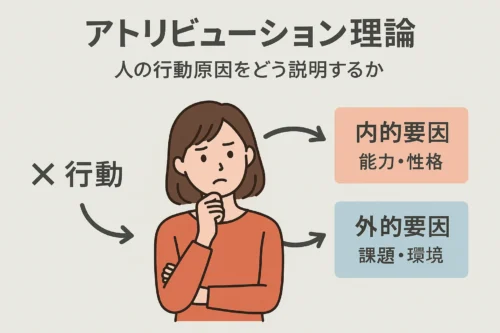毎日40人・年間1万人以上と会話しているRyoです。
薬局の管理薬剤師になった頃、スタッフから「Ryoさんって話聞いてくれないよね」と言われたのが衝撃でした。
そこから聞く力を鍛え直した経験を、リーダー視点で包み隠さず共有します。
リーダーの「聞く力」はなぜ重要なのか
情報の質が意思決定を左右する
リーダーは判断を迫られる立場。判断材料が偏っていたら、チームは迷走します。聞く力が弱いと、声の大きい人の意見ばかり拾い、静かなメンバーの違和感を見落とす。僕も在庫トラブルのとき、積極的なスタッフの声だけを信じて対応した結果、現場はさらに混乱しました。全員の声を引き出す耳こそ、意思決定の土台です。
信頼は「話を聴いてもらえた」実感から生まれる
人は、話を最後まで聴いてもらえた相手に心を開きます。「意見が採用されたかどうか」より「否定されずに聴いてくれたか」が、チームの信頼残高を決める。僕がスタッフ面談で沈黙に付き合ったとき、相手が「黙って待ってくれるだけで安心する」と言ってくれたのが忘れられません。
エラー兆候の早期発見につながる
現場では小さなヒヤリが毎日起きます。聞く力があれば、雑談に紛れた違和感を拾い、「それってどういう状況?」と深掘りできる。これがヒヤリハットの芽を摘む最速ルートです。
僕がやらかした「聞けてない」失敗談
失敗1:焦って結論を押し付けた
新人が「入力が追いつかない」と相談してきたとき、僕は「このショートカット覚えれば?」と即アドバイス。新人は無言になり、翌日には別の先輩に相談していました。実は「作業の意味が理解できず不安」だったのに、僕は効率だけを押し付けていた。原因は「何が困ってるの?」と聞き切れていなかったことでした。
失敗2:共感の言葉を飛ばした
クレーム対応後に泣きそうなスタッフへ「次はこうしよう」と改善案を連発。スタッフは心を閉ざし、「もう相談しません」と言い残して帰宅。まず「大変だったね」「よく耐えたね」と感情を受け止める耳が必要だと痛感しました。
失敗3:沈黙を怖がった
面談で部下が沈黙すると、すぐにこちらから喋ってしまう癖がありました。沈黙の後に出てくる言葉こそ本音なのに、僕はそのチャンスを潰していた。沈黙に耐える練習は今も続けています。
聞く力を磨く基本スキル
1. 受容の姿勢
相手の話を遮らず、表情と頷きで「受け止めているよ」と伝えます。椅子の角度を相手に合わせ、身体を少し前傾に。薬局カウンターでも、画面を見ながら聞くと「聞いてない」と思われるので、手を止めるようにしています。
2. 感情の反射(エモーショナルリフレクション)
「それはしんどかったね」「ワクワクしてるんだね」と感情を言語化して返す。言葉にしてもらった瞬間、人は自分の感情を客観視できます。僕が新人の不安を「焦ってるんだね」と返したとき、「そう、焦ってるんです」と涙が溢れ、そこから本音の相談につながりました。
3. 意図を確認する質問
話の背景を確かめる「そのとき何を大事にしてたの?」などの質問で、相手の価値観を探ります。意図を理解することで、アドバイスの的が絞れます。
4. 共感と要約
最後に要点を整理して確認。「つまり、○○が不安で、□□をどうにかしたいんだね?」と要約すると、相手は安心します。要約は理解を示す最高の証拠です。
具体的な聞く力トレーニング
週次「聞き役ローテーション」
僕の薬局では週1回、5分の「聞き役トレーニング」をしています。話し手と聞き手に分かれて、聞き手は一切アドバイス禁止。相手の話を要約して返すだけ。終わったら「どんな反応が嬉しかった?」と振り返り、気づきを共有します。
沈黙耐性を鍛えるカウント法
面談中の沈黙で落ち着かないときは、心の中で5まで数えます。5秒待つだけで、相手から本音が出てくる確率がぐんと上がる。僕は最初3秒が限界でしたが、訓練を続けて10秒待てるようになりました。
感情語ボキャブラリーを増やす
聞く力が弱いと、返す言葉が「大変ですね」「頑張ってますね」の二択になりがち。僕は感情リストを作って「ざわざわ」「もやもや」「ホッとした」など50語を書き出し、面談前に眺めています。語彙が増えると、相手の気持ちをピタッと表現できるようになります。
ノートで「聞いたこと」を可視化
面談が終わったら、「事実」「感情」「願い」の3列でノートに整理します。書き出すことで、自分がどこまで聞けたか振り返れます。漏れが多いときは「質問が浅かったな」と反省し、次回の問いを準備します。
チーム運営に活かす聞く力
朝礼のミニヒアリング
朝礼で「昨晩の睡眠スコア」「今日の体調」を一言で共有してもらう。僕は「体力3/5です」「テンション高め」など数値と感情の両方を聞くようにしています。これでシフト調整やフォローがしやすくなります。
業務後の1分フィードバック
閉店後、「今日のハイライト」と「モヤモヤ」を1分ずつ話してもらうミニ振り返りを実施。リーダーは聞くだけ。感情を受け取る習慣ができ、ヒヤリ情報が早く上がってくるようになりました。
チャットでも“聞く姿勢”を伝える
文字のコミュニケーションでも、「今は大丈夫?」「落ち着いたら教えてね」と相手のペースを尊重する言葉を入れます。既読スルーされても焦らない。聞く力はリアルタイムだけでなく、非同期にも表れます。
エピソード:聞く力で変わった現場
事例1:離職寸前のスタッフが踏みとどまった
あるスタッフが「もう辞めたい」と涙を溜めて面談に来ました。以前の僕なら「頑張ろう」と励まして終わっていたでしょう。今回はひたすら聞き、彼女が口にした「家で愚痴れない」という言葉を拾って、「職場で愚痴を吐ける時間を作ろう」と提案。週1回の雑談タイムを作ると、彼女は「話を聞いてもらえただけで心が軽くなった」と続けてくれました。
事例2:クレーム連鎖を止めたヒアリング
待ち時間が長くクレームが続いた日、僕はスタッフ全員から「何が起きてた?」と聞き取り。話をまとめると「電話対応が一人に集中していた」が原因だと判明。聞く力で事実が整理できたおかげで、すぐに役割分担を調整でき、翌日はクレームゼロに。
事例3:医師との連携がスムーズに
在宅訪問で医師がイライラしていたとき、僕は「先生、一番気になっているのはどのポイントですか?」と聞きました。医師は「血圧の推移がわからないこと」と本音を吐露。すぐにデータを共有し、「助かったよ」と信頼を得られました。専門家同士でも、聞く力が関係を動かします。
リーダーが陥りやすい落とし穴と対策
落とし穴1:成果を急ぎすぎる
聞く→考える→決めるのサイクルを短縮しようとすると、聞く工程が雑になります。対策は「聞く時間をスケジュールに入れる」。面談30分なら、そのうち20分は聞く時間と決めてしまう。時間が確保されると、焦りが消えます。
落とし穴2:アドバイス癖
経験があるほど「こうすべき」が浮かびます。僕はノートに「結論を急ぐな」と書いて目の前に貼り付けました。相手が「アドバイスが欲しい」と言うまで、ひたすら質問と共感に徹するルールを自分に課しています。
落とし穴3:価値観の押し付け
「私はこうやってきた」が口癖になると、部下は意見を出さなくなります。相手の価値観を理解する質問、「なぜそれが大事?」を忘れずに。価値観を尊重した上で提案すると、受け入れやすくなります。
ハイブリッドワーク時代の聞く力
オンライン1on1の工夫
画面越しだと表情が読みづらいので、僕は最初の5分で「今日の気分を色で表すと?」と聞き、感情の温度を把握します。また、ノイズを減らすために通知を切り、メモは手書きで。タイピング音がすると「ちゃんと聞いてる?」と不安にさせます。
チャットヒアリングのテンプレ
- 「今、何に一番時間を取られてる?」
- 「困り事は“緊急”と“重要”どっち?」
- 「いつなら詳しく話せそう?」
短い問いで相手の状況と優先度を把握し、必要なら通話に切り替えます。
離れていても“聞いている”を見せる
週報にコメントを書くとき、「ここが心配に感じた」「この点、もっと聞かせて」と問いを添えます。顔が見えなくても、耳を傾けている姿勢を届けられます。
聞く文化をチームに根付かせる
共有ボードで「聞いて得た学び」を記録
スタッフが患者さんや同僚から聞いた気づきを、共有ボードに一言で残す。「○○さん、夜間に足がつる」「新人B、確認方法が不安」といったメモが蓄積すると、チーム全体で傾聴の価値を再確認できます。
表彰制度に「聞く賞」を追加
月末に「一番聞いてくれた人」を投票し、ちょっとしたギフトを渡します。評価されることで「聞くこと」が行動指針として定着します。僕の薬局では「聞く賞」を始めてから、雑談の時間が増え、心理的安全性が高まったと感じます。
反省会で「聞き逃したこと」を共有
トラブル後の振り返りでは、「何を聞き逃していたか」を必ず議題にします。「患者さんの表情に気づけなかった」「スタッフの不安をスルーしていた」といった振り返りが次の改善に直結します。
聞く力を測るセルフチェックシート
- 相手の言葉を途中で遮っていないか
- 共感の言葉を3種類以上使えているか
- 要約を最後に返しているか
- 聞いた内容を翌日も覚えているか
- 相手の変化に気づいたら声をかけているか
このシートを週1回振り返ると、自分の聞く力の伸びが見える化します。僕もチェックし忘れる週は、やっぱり面談が雑になります。
ケース別:聞く力の応用編
クライアントへのヒアリング
BtoB営業でも聞く力は必須。僕は「導入後にどんな未来を描いていますか?」と聞いて、相手の成功イメージを共有します。その上で「一番不安なのは何ですか?」と聞き、リスク対策を一緒に考えます。
トラブル時の初動
スタッフから「やばいです」と連絡が来たら、まず「今、何が見えてる?」と情報を整理。次に「どう感じてる?」と感情を受け止め、「最初の一歩として何ができそう?」と一緒に考えます。聞く力をフル活用すると、パニックが収まります。
多職種連携
医師や看護師とのカンファレンスでは、「それぞれの立場で一番重視していることは?」と順番に聞いていきます。価値観の差が表面化し、調整がスムーズになります。
聞く力を阻む要因とリセット方法
忙しさ
忙しいと耳が狭くなります。僕は忙しい日の朝に「今日は余白を作る」と手帳に書き、敢えて5分の空白時間を確保します。余裕があるだけで、聞き方の質が変わります。
感情の高ぶり
自分の感情が高ぶっているときは、深呼吸して心拍を落ち着かせます。面談前にトイレで10秒瞑想するだけでも効果的。心が整うと、相手の言葉が入ってきます。
偏見
「あの人はいつも遅い」などの先入観があると、話を歪めて受け取ってしまいます。先入観に気づいたら、「今回はどうかな?」と自分に問い直す。真っ白な耳で聞き直す習慣が大切です。
聞く力を高めるリーダーの習慣
1日の終わりに聞き取りログを書く
「今日、誰の声をどれくらい聞けたか」「感情を受け止められたか」をノートに記録します。数が少ない日は翌日にリベンジ。聞く力は日記で伸びます。
読書より“人の話”をインプット
学びたいとき、僕は本だけでなく他部署のリーダーに話を聞きに行きます。「最近困ってることは?」と質問し、他業種の知恵を吸収。聞く力の幅が広がります。
定期的に第三者の耳を借りる
外部コーチやメンターに自分の聞き方をフィードバックしてもらうのも有効です。「質問が連発しすぎ」と指摘されたことがあります。客観的な耳が自分を育ててくれます。
まとめ:聞く力はリーダーの最大の投資
リーダーにとって聞く力は、チームの未来への投資です。焦らず、感情を受け止め、価値観を尊重する耳を育てるほど、チームの信頼残高は増えていきます。面倒でも、今日の会議で一人ひとりに「他に伝えたいことは?」と聞いてみてください。その一言が、チームの空気を静かに変えていきます。
聞く力を伸ばすロードマップ
月ごとの目標設定
1か月目は「遮らない」をテーマに、面談や雑談で相手の話を最後まで聞き切ることだけを意識します。2か月目は「感情を返す」、3か月目は「要約する」。テーマを一つずつ積み上げると、聞く力が段階的に伸びていきます。
毎日のマイクロ習慣
- 朝礼前に深呼吸を3回
- 面談メモに「聞いた言葉ベスト3」を書く
- 帰宅前に「今日ありがとうを伝えた相手」を振り返る
小さな習慣を積み重ねると、耳が自然と研ぎ澄まされます。
感情を見抜く観察ポイント
目線とまばたき
相手の視線が泳いでいたら、緊張や不安を抱えているサイン。まばたきが増えたら、情報が多すぎて処理が追いついていない可能性があります。僕は「情報量多かったよね」と声をかけ、ペースを落とすようにしています。
手元の動き
ペンを握りしめる、指を組むなどの動きは、感情が高ぶっている証拠。こういうときは「今、胸のあたりがざわざわしてる?」と感情を言葉にして返すと安心してくれます。
声のボリューム
声が急に小さくなったら、話題を変えてほしいサインかもしれません。「この話題、別のタイミングにする?」と確認するだけで、相手のストレスが減ります。
聞き漏れを防ぐチェックリスト
- 事実・感情・希望の3要素が揃っているか
- 相手の言葉をメモに残したか
- 次回フォローの日時を確認したか
- 自分の解釈を押し付けていないか
- 最後に「他に伝えておきたいことある?」と聞いたか
このチェックを面談ごとに回すと、聞き漏れがぐっと減ります。僕はチェックリストをラミネートして、ノートの表紙に貼っています。
現場で実感した効果
1. ヒヤリハット報告が倍増
聞く力を鍛え始めて半年、ヒヤリハット報告数が2倍になりました。これは悪いことではなく、危険が表に出てきた証拠。スタッフが安心して話せると、リスクが早期に共有されるようになります。
2. 患者満足度のコメントが変化
アンケートの自由記述で「話をよく聞いてくれる」「質問しやすい」と書かれるようになりました。リーダーの聞き方が、チーム全体の受け答えに影響していると実感しました。
3. 会議の時間短縮
以前は会議で議論が迷子になりがちでしたが、聞く力を意識してからは要点を要約しながら進行できるようになり、会議時間が15分短縮。余裕が生まれたことで、振り返りの時間も確保できました。
忙しい日でも耳を開くための工夫
スマホリマインダー
午後のピーク前に「耳を開く」と通知が来るように設定しています。たった一言のリマインドでも、気持ちが切り替わります。
立ち話ミーティング
座る時間がない日は、廊下で2分だけ立ち話。「今一番助けてほしいことある?」と聞くだけで、要点をサッと拾えます。短時間でも「聞いてもらった」感は伝わります。
自分のコンディション共有
リーダー自身も「今日は寝不足で判断が遅いかも」と先に伝えておくと、スタッフがサポートしてくれます。自分の状態を開示することも、聞く力の一部です。
よくある質問と回答
Q. 「忙しい」を理由に断ってもいい?
A. 正直に「今は時間が取れないから、○時に話を聞かせて」と約束を入れましょう。約束を守れば信頼は損なわれません。曖昧にすると相手は不安になります。
Q. 感情的になった相手にどう対応する?
A. まずは感情を受け止め、「怒ってるのは当たり前だよ」と共感します。落ち着いてから事実確認に移る。順番を間違えると火に油です。
Q. アドバイスを求められたら?
A. 「まずは整理させて」と言って要点を要約し、相手と解決策を一緒に考えます。アドバイスを出すにしても、相手の言葉を基にすることが大切です。
聞く力をチームに教えるワークショップ例
- 聞き上手な人のエピソードを共有(10分)
- 2人ペアで聞き手・話し手に分かれてロールプレイ(15分)
- 感じたことを付箋に書き出し、ボードに貼る(10分)
- リーダーがまとめと次のアクションを提示(5分)
短時間でも学びが濃くなるので、月1回の研修に組み込んでいます。
まとめ直前のセルフ問いかけ
- 今日、誰の声にありがとうと言えた?
- 相手の価値観に触れられた瞬間はあった?
- 次に会うとき、どんな質問から始めたい?
この問いを手帳に書いておくと、日々の聞き方が磨かれていきます。
聞く力の未来予測と僕の宣言
AIや自動化が進んでも、最後に価値を決めるのは人の感情です。だからこそリーダーの聞く力は、これからますます差別化要因になります。僕自身、「今日も耳からチームを整える」と朝に宣言するようになってから、スタッフの表情が柔らかくなった気がします。聞くことは地味だけど、誰よりも強いリーダーの武器です。
最後にもう一歩踏み出すために
今この瞬間、耳を澄ませたい相手の顔を一人思い浮かべてください。想像するだけで、次に会ったときの第一声が変わります。「最近どう?」の代わりに「今、一番大事にしたいことは?」と聞いてみる。たったそれだけで、会話の深さは段違いです。リーダーの聞く力は、日常の小さな問いかけから磨かれていきます。
聞く力は才能じゃない、積み重ねです。僕もまだまだ修行中。でも耳を開けば開くほど、チームの景色が鮮やかになる。そんな変化を、一緒に体験していきましょう。