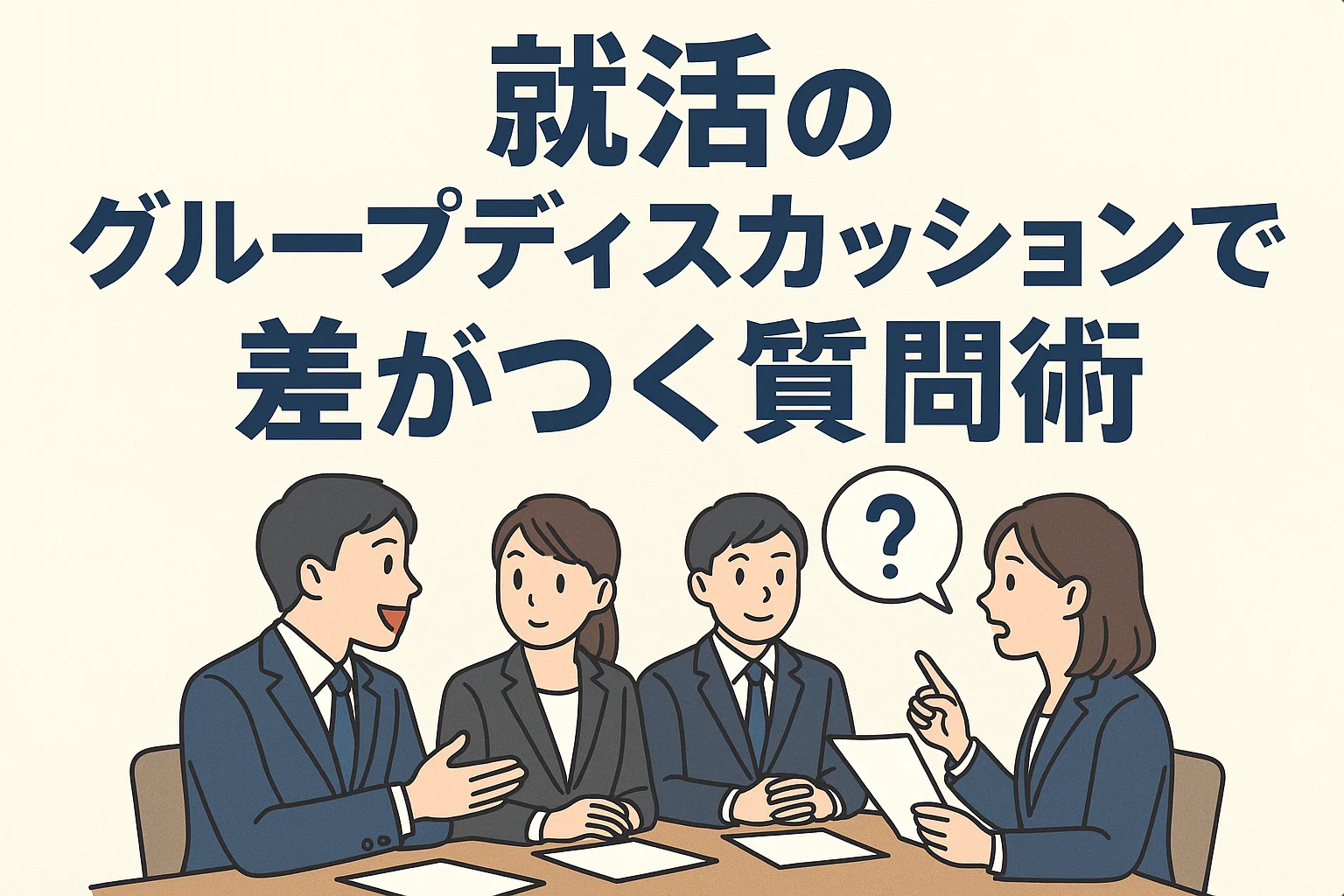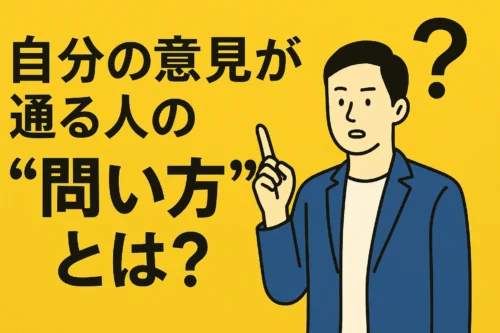毎日薬局で40人のお客様と会話しているRyoです
就活のグループディスカッションって、緊張しますよね。特に「何を話せばいいかわからない」「他の人に流されてしまう」って悩みが多い。
僕も就活の時はそうでした。グループディスカッションで「何か意見を言わなきゃ…」って焦って、結局何も言えずに終わってしまうことが多かったんです。
でも、実は**「質問術」**を覚えるだけで、誰でもグループディスカッションで差をつけることができるんです。難しいテクニックは必要ありません。
グループディスカッションで差がつかない理由
多くの人がグループディスカッションで差がつかない理由は、実はシンプルです。それは「質問の仕方が間違っている」んです。
どういうことかというと、相手の意見を聞いているつもりが、実は「次に何を言おうか」ばかり考えているんです。すると、相手の意見を深く理解できず、表面的な議論になってしまう。
これ、僕もよくやってました。他の人が「この商品は若者向けに…」って意見を言っても、「なるほど」で終わってしまい、深掘りできなかったんです。
グループディスカッションで差がつく質問術
質問術1:「なぜ?」で理由を深掘りする
他の人の意見が終わったら、「なぜそう思うんですか?」と理由を聞いてみましょう。これで、相手の考え方がより深くわかります。
例えば、他の人が「この商品は若者向けにアピールすべき」と言ったら、「なぜ若者向けだと思われますか?」と聞くんです。
すると、相手が「若者はSNSをよく使うから、拡散されやすい」とか「若者は新しいものに興味があるから」とか、具体的な理由を話してくれます。
質問術2:「もしも」で仮定の状況を考える
相手の意見が終わったら、「もしも〜だったら、どうしますか?」と仮定の質問をしてみましょう。これで、相手の考え方がより深くわかります。
「もしも、若者が興味を持たなかったら、どうしますか?」と聞くと、「中高年向けのアピールも並行して行う」とか「商品の特徴を変える」とか、相手の柔軟性がわかります。
質問術3:「具体的には?」で実行方法を聞く
相手の意見が終わったら、「具体的には、どのように行いますか?」と実行方法を聞いてみましょう。これで、相手の実現可能性がわかります。
「具体的には、どのように若者にアピールしますか?」と聞くと、「インスタグラムでインフルエンサーを使う」とか「TikTokで動画広告を出す」とか、具体的な方法がわかります。
実践してみた結果
僕がこの「質問術」を使い始めてから、グループディスカッションでの評価が変わりました。
以前なら「なるほど」で終わってしまっていた議論が、今は「なぜそう思うんですか?」「具体的にはどうしますか?」と深掘りできるようになったんです。
すると、面接官から「他の人の意見を深掘りできている」と評価されるようになり、グループディスカッションで高評価をもらえるようになりました。
質問術を使う際の注意点
注意点1:相手の意見を否定しない
「でも、それは違うと思います」とか「それは無理だと思います」とか、相手の意見を否定しないでください。相手の意見を深掘りすることが目的です。
注意点2:質問ばかりにならない
質問ばかりだと、自分の意見を言っていないと思われます。適度に自分の意見も言いましょう。
注意点3:時間を意識する
グループディスカッションは時間が限られています。質問は簡潔に、相手の答えも適切な長さで聞きましょう。
フォローアップクエスチョンの活用
グループディスカッションで差をつけるためには、適切なフォローアップクエスチョンも大切です。相手の意見を深掘りすることで、より深い議論ができます。
フォローアップクエスチョンについてもっと詳しく知りたい方は、こちらの記事もどうぞ→フォローアップクエスチョンとは?例文と使い方まとめ
まとめ
就活のグループディスカッションで差がつく質問術は、難しいテクニックではありません。以下の3つを意識するだけです:
- 「なぜ?」で理由を深掘りする
- 「もしも」で仮定の状況を考える
- 「具体的には?」で実行方法を聞く
この3つの質問術を使うだけで、あなたもグループディスカッションで差をつけることができます。
僕もまだまだ勉強中ですが、この「質問術」を使うようになってから、グループディスカッションでの評価が格段に良くなりました。あなたも今日から試してみませんか?