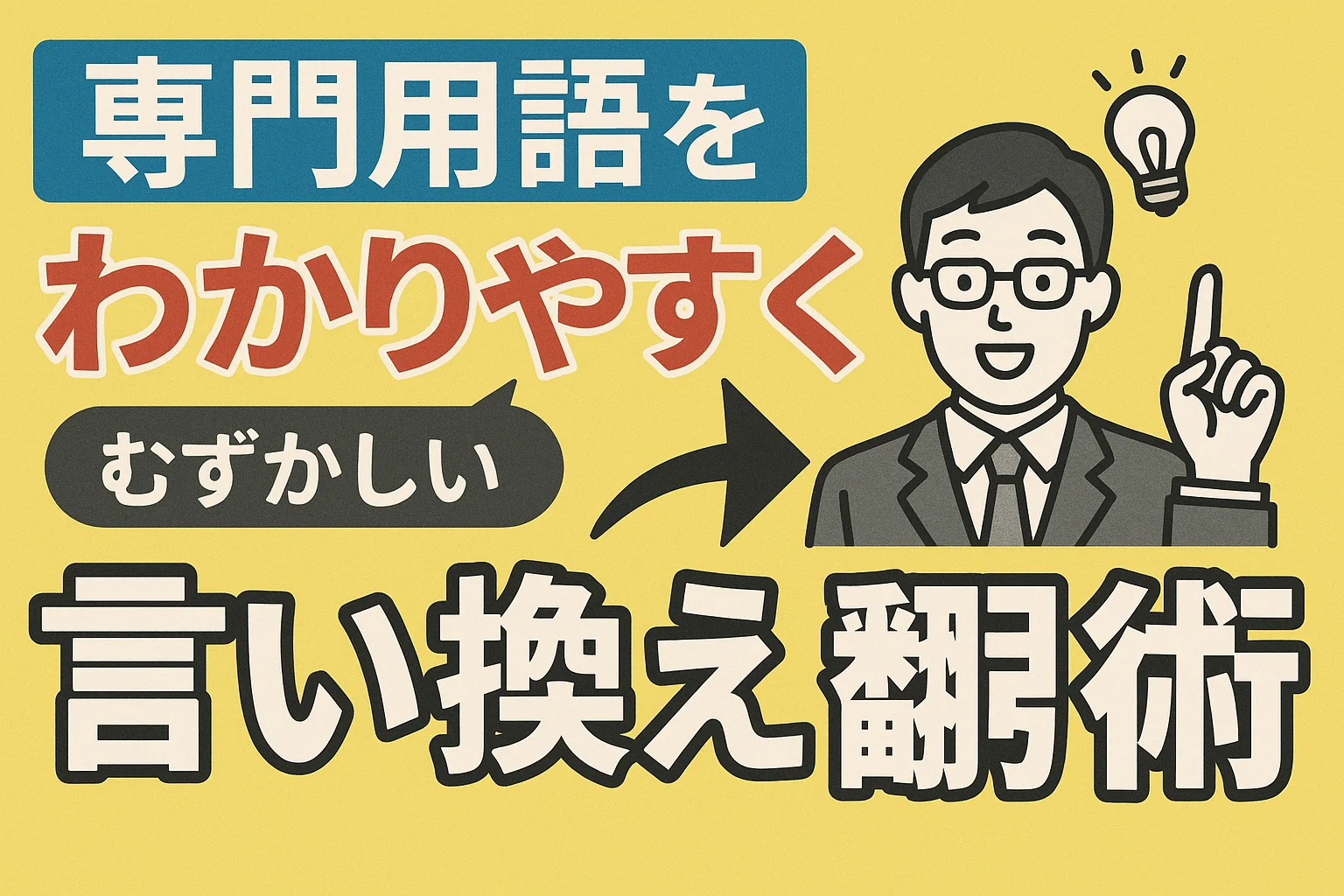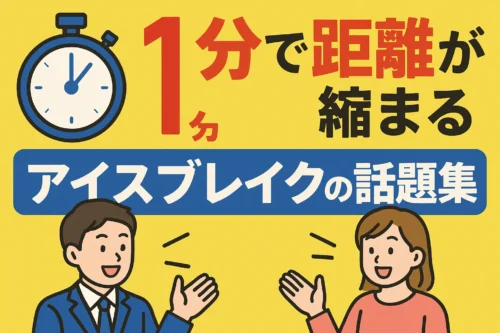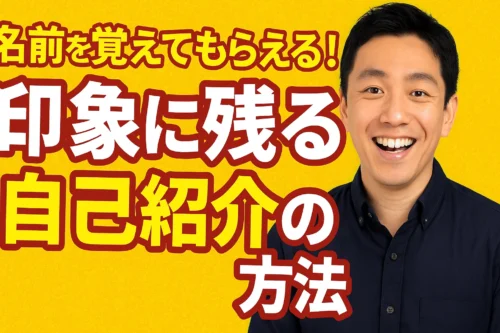毎日40人・年間1万人以上と会話しているRyoです。薬の説明をしてて、専門用語を使うと患者さんがポカンとした表情になること、ありませんか?
「副作用」「併用禁忌」「半減期」…薬剤師には当たり前の言葉でも、患者さんには暗号みたいなものです。でも専門用語を全く使わないのも、正確性に欠けちゃう。
今日は年間1万人への説明で磨いた、専門用語をわかりやすく「翻訳」するテクニックをお話しします。
なぜ専門用語の翻訳が必要なのか?
薬剤師と患者さんの間には、知識の大きな差があります。
私たちが当たり前に使ってる言葉が、患者さんには理解できない。でも理解できないまま薬を飲んでもらうのは、安全性の面でもリスクがあります。
私も新人の頃は、「この薬はCYP3A4で代謝されるので…」とか専門用語をそのまま使ってました。患者さんの困惑した表情を見て、「もっとわかりやすく伝えないと」って気づいたんです。
でも単純に「簡単な言葉に変える」だけじゃダメ。正確性を保ちながら、相手のレベルに合わせて「翻訳」することが大切です。
基本的な翻訳パターン
1. 具体例で説明するパターン
専門用語: 副作用
翻訳: 「お薬を飲むことで起こる可能性がある、体の変化のことです。例えば、眠くなったり、お腹が痛くなったりすることがあります」
専門用語: 相互作用
翻訳: 「お薬同士がお互いに影響し合うことです。例えば、Aのお薬がBのお薬の効き方を強くしたり、弱くしたりすることがあります」
2. 身近なものに例えるパターン
専門用語: 半減期
翻訳: 「お薬の量が体の中で半分になるまでの時間です。お風呂のお湯が冷めていくように、お薬も時間とともに体から減っていきます」
専門用語: 血中濃度
翻訳: 「血液の中にお薬がどのくらい含まれているかということです。コーヒーの濃さのように、お薬にも濃さがあります」
3. 機能を説明するパターン
専門用語: ACE阻害薬
翻訳: 「血管を広げて血圧を下げるお薬です」
専門用語: プロトンポンプ阻害薬
翻訳: 「胃酸の出る量を減らすお薬です」
年代別翻訳テクニック
高齢者向け(70代以上)
特徴:
- ゆっくりとした説明を好む
- 身近な例えが効果的
- 繰り返し説明が必要
翻訳例:
専門用語: 降圧薬
高齢者向け翻訳: 「血圧を下げるお薬です。血管の中を流れる血の勢いを、穏やかにしてくれます」
働き世代向け(30-60代)
特徴:
- 効率的な説明を求める
- 日常生活への影響を重視
- ある程度の医学知識がある
翻訳例:
専門用語: 徐放錠
働き世代向け翻訳: 「ゆっくりと溶けて、長時間効果が続くお薬です。1日1回で24時間効いてくれるので、飲み忘れが少なくなります」
子育て世代向け
特徴:
- 家族への影響を心配
- 安全性を重視
- 具体的な注意点を求める
翻訳例:
専門用語: 催眠薬
子育て世代向け翻訳: 「眠りを助けるお薬です。お子さんの世話に影響が出ないよう、飲むタイミングを一緒に相談しましょう」
シチュエーション別翻訳術
初回処方時
初めての薬について説明する時は、特に丁寧な翻訳が必要です。
例:糖尿病薬の説明
専門用語版: 「DPP-4阻害薬でインクレチンの分解を阻害し、グルコース依存的にインスリン分泌を促進します」
翻訳版: 「血糖値を下げるお薬です。食事をした時だけ働いて、血糖値が上がりすぎないようにコントロールしてくれます。お腹が空いている時は働かないので、低血糖になりにくいのが特徴です」
薬が変更になった時
変更理由を含めて説明するため、比較しながら翻訳します。
例:血圧薬の変更
専門用語版: 「ACE阻害薬からARBに変更になります」
翻訳版: 「血圧を下げるお薬の種類を変更します。どちらも血管を広げて血圧を下げる働きは同じですが、新しいお薬の方が空咳という副作用が起こりにくいです」
副作用の説明時
不安を与えすぎないよう、でも正確に伝える翻訳が重要です。
例:抗ヒスタミン薬
専門用語版: 「H1受容体拮抗薬による中枢神経抑制作用」
翻訳版: 「眠気が出る可能性があります。アレルギーを抑える成分が、脳の覚醒を維持する部分にも少し影響するためです。個人差がありますが、特に飲み始めの数日間は注意してください」
効果的な翻訳のコツ
1. 段階的説明法
複雑な概念は、段階を分けて説明します。
例:薬物動態
- 「お薬を飲むと、まず胃や腸で溶けます」
- 「溶けたお薬は血液に入ります」
- 「血液に乗って、必要な場所に運ばれます」
- 「役目を終えたお薬は、肝臓で処理されて体の外に出ます」
2. 数値の可視化
抽象的な数値を具体的にイメージできるようにします。
例:副作用の発現率
専門用語: 「副作用発現率5%」
翻訳: 「100人の方が飲んだとすると、5人の方に何らかの副作用が現れる可能性があります」
3. ポジティブ変換
ネガティブな印象を与えがちな専門用語を、前向きに翻訳します。
専門用語: 薬物依存
翻訳: 「お薬に体が慣れてしまうことがあります。そのため、止める時は医師と相談しながら、少しずつ減らしていきます」
翻訳時の注意点
1. 正確性を失わない
わかりやすくしようとして、医学的に不正確になってはいけません。
NG例:
血圧薬を「血液をサラサラにする薬」と説明
→ 抗凝固薬と混同される可能性
OK例:
「血管を広げて、血液の流れを良くする薬」
2. 不安を煽らない
副作用の説明などで、必要以上に不安を与えないよう注意。
NG例:
「危険な副作用が起こる可能性があります」
OK例:
「注意していただきたい症状があります。でも早めに気づけば対処できますので、一緒に気をつけていきましょう」
3. 個人差を考慮
同じ翻訳が全ての患者さんに適用できるわけではありません。
相手の反応を見ながら、説明のレベルを調整することが大切です。
実際の翻訳事例集
よく使う専門用語の翻訳リスト
薬効関連:
- 抗炎症作用 → 炎症(腫れや痛み)を抑える働き
- 鎮痛作用 → 痛みを和らげる働き
- 抗菌作用 → 細菌をやっつける働き
- 解熱作用 → 熱を下げる働き
服用方法関連:
- 頓服 → 症状が出た時に飲むお薬
- 定時服用 → 毎日決まった時間に飲むお薬
- 空腹時服用 → 食事の前に飲むお薬
- 食間服用 → 食事と食事の間に飲むお薬
副作用関連:
- 消化器症状 → 胃腸の調子が悪くなること
- 皮膚症状 → 肌に現れる変化(発疹、かゆみなど)
- 中枢神経症状 → 眠気やめまいなどの症状
まとめ:患者さん目線の翻訳を心がけて
専門用語の翻訳は、患者さんとの架け橋になる重要なスキルです。
ポイントまとめ:
- 具体例や身近な例で説明
- 年代や状況に合わせて調整
- 段階的に理解を深める
- 正確性を保ちながらわかりやすく
- 不安を煽らない表現を選ぶ
完璧な翻訳ができなくても大丈夫。大切なのは「患者さんにとってわかりやすく伝えたい」という気持ちです。
私も毎日の接客で、より良い翻訳方法を模索してます。患者さんから「よくわかりました」って言ってもらえた時の嬉しさは格別です。
明日からの薬の説明で、ぜひ「翻訳」を意識してみてください。患者さんの理解度と満足度が、きっと変わりますよ!