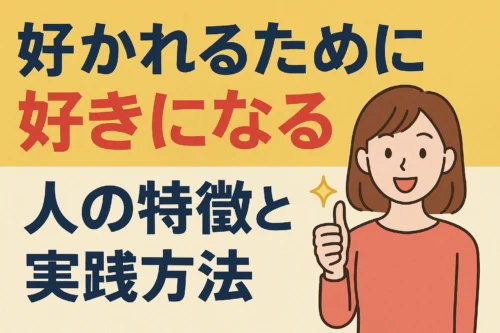毎日40人・年間1万人以上と会話しているRyoです。
薬局で患者さんと話していると、言葉では「大丈夫です」って言っているのに、表情や声のトーンから「実は心配している」って伝わってくることがあるんですよね。
これって、メラビアンの法則が関係しているんです。
メラビアンの法則とは
7-38-55の法則
メラビアンの法則は、コミュニケーションにおいて相手に与える印象の割合を示したものです:
- 言語情報(話の内容): 7%
- 聴覚情報(声のトーン・速さ・大きさ): 38%
- 視覚情報(表情・仕草・姿勢): 55%
つまり、言葉の内容よりも、表情や声の調子の方が相手に与える印象が大きいということです。
なぜ非言語コミュニケーションが重要なのか
人間の脳は、言葉よりも表情や声の調子を優先的に処理するようにできているんです。これは、太古の昔から危険を察知するために発達した能力だと言われています。
薬局での実際の体験談
患者さんが不安そうな時
ある日、高血圧の薬を処方された患者さんが「大丈夫です」って言いながら、手が震えていたんです。
言葉では「大丈夫」と言っているのに、手の震えや表情から不安が伝わってきました。この時、私は言葉だけでなく、患者さんの表情や仕草にも注目するようにしたんです。
声のトーンでわかる体調の変化
風邪薬を処方した患者さんが、1週間後に来店した時。「もう大丈夫です」って言っていたんですが、声がかすれていて、表情も少し暗かったんです。
言葉では「大丈夫」と言っているのに、声のトーンから「まだ完全には治っていない」ってことがわかったので、追加のケアを提案しました。
非言語コミュニケーションを活用する方法
1. 表情を意識する
笑顔は相手に安心感を与える最強の武器です。特に初対面の人には、自然な笑顔を見せるようにしています。
実践例:
- 患者さんが来店したら、まず笑顔で挨拶
- 薬の説明中も、時々笑顔を交える
- 不安そうな患者さんには、より温かい表情で接する
2. 声のトーンを調整する
同じ言葉でも、声のトーンが違うと相手に与える印象が全く変わります。
実践例:
- 真面目な話の時は、少し低めの声でゆっくり話す
- 楽しい話の時は、明るい声で話す
- 患者さんが不安そうな時は、優しい声のトーンで話す
3. 姿勢と仕草を意識する
姿勢が悪いと、相手に「この人、大丈夫かな」って思われちゃいます。
実践例:
- 患者さんと話す時は、相手の目を見て話す
- 薬の説明中は、適度に身振り手振りを交える
- 患者さんの話を聞く時は、前かがみになって聞く
メラビアンの法則を活用した接客術
信頼関係を築くためのポイント
-
第一印象を大切にする
- 清潔感のある服装
- 自然な笑顔
- 適切な挨拶
-
相手の非言語サインを読み取る
- 表情の変化
- 声のトーンの変化
- 仕草や姿勢の変化
-
自分の非言語サインをコントロールする
- 緊張している時は深呼吸
- 疲れている時は、少し明るい声で話す
- 不安な時は、自信を持った姿勢を保つ
日常会話での実践例
友人との会話
「最近、どう?」と聞かれた時、言葉では「まあまあ」と答えていても、表情が暗かったり、声が小さかったりすると、相手に「何かあったのかな」って心配されます。
職場での会議
会議で意見を言う時、内容が良くても、声が小さかったり、下を向いていたりすると、説得力がなくなっちゃいます。
注意点とよくある誤解
メラビアンの法則の誤解
メラビアンの法則は「言葉は7%しか意味がない」という意味ではありません。言葉が重要でないということではなく、非言語コミュニケーションも同じくらい重要だということです。
バランスの大切さ
言葉の内容、声のトーン、表情や仕草、これらが一致していることが最も効果的です。言葉と表情が違うと、相手に違和感を与えてしまいます。
まとめ
メラビアンの法則から学べることは、コミュニケーションにおいて非言語的な要素が非常に重要だということです。
具体的には:
- 表情を意識する(55%の影響)
- 声のトーンを調整する(38%の影響)
- 姿勢と仕草を意識する
- 相手の非言語サインを読み取る
これらの要素を意識することで、より効果的なコミュニケーションができるようになります。
ただし、言葉の内容も大切です。非言語コミュニケーションとバランスを取って、相手に伝えたいことを正確に伝えることが重要です。
薬局での接客を通じて、メラビアンの法則の重要性を実感しています。ぜひ、日常のコミュニケーションでも意識してみてくださいね。