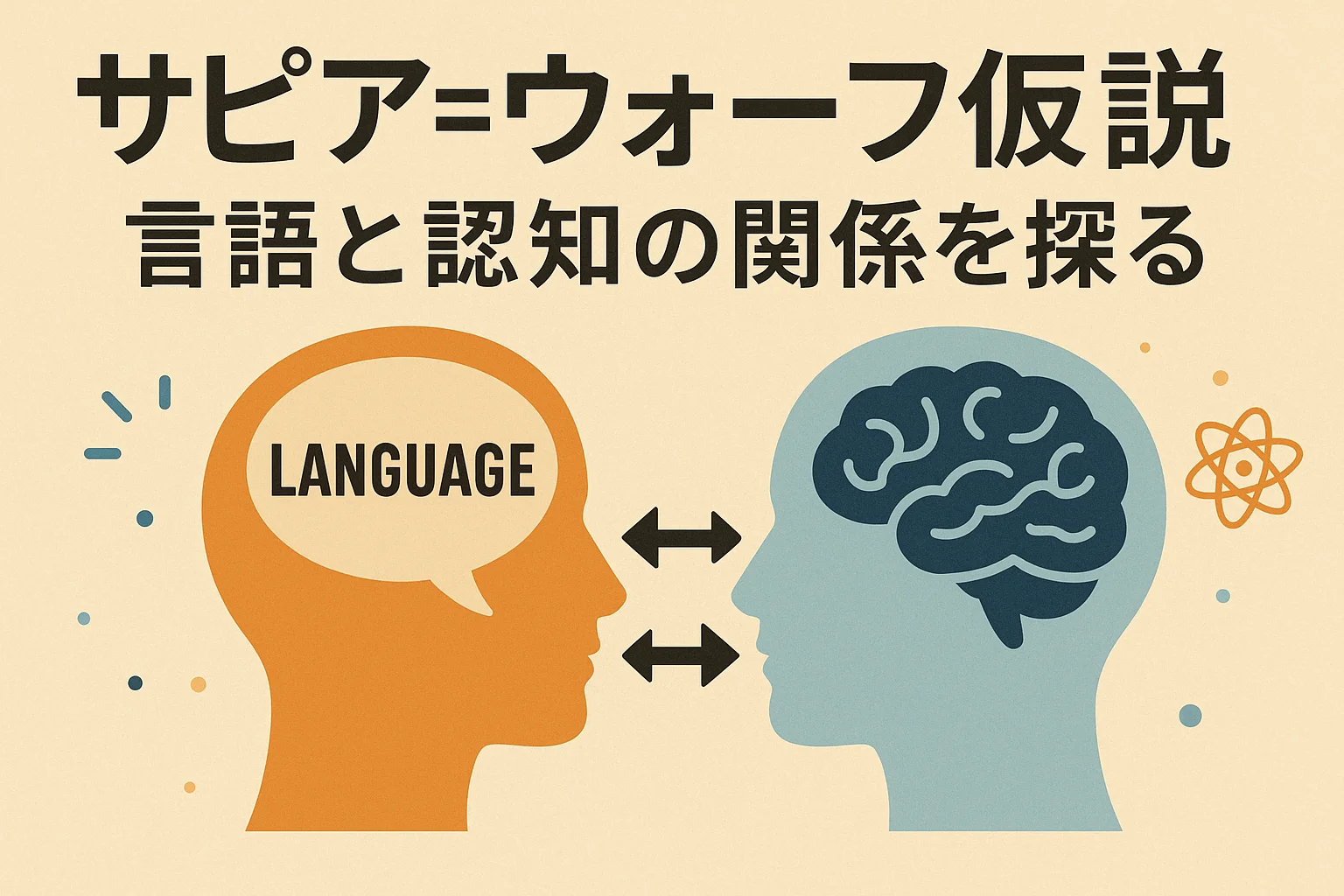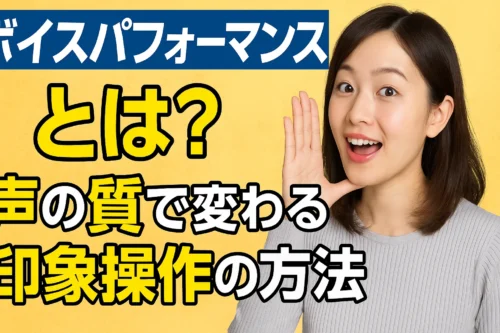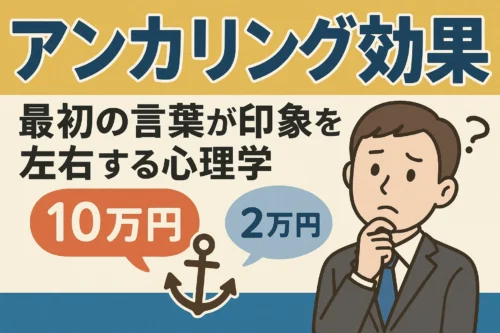毎日40人・年間1万人以上と会話しているRyoです。
サピア=ウォーフ仮説は、言語が思考や認知に影響を与えるという大胆な考え方です。薬局で患者さんと話していると、言葉の使い方ひとつで理解や反応が変わる瞬間に何度も遭遇します。今回はこの仮説を、現場での体験とともにわかりやすく紹介します。
サピア=ウォーフ仮説の基礎
エドワード・サピアとベンジャミン・ウォーフという2人の研究者が唱えた説で、「言語は人の思考を規定する」と考えます。完全に支配するとまでは言い過ぎですが、言語が思考の枠組みを作るという点では現場でも実感があります。
言語と認知が交わる瞬間
時制の違いが生む時間感覚
英語では過去・現在・未来をはっきり区別しますが、日本語は文脈で曖昧にできることが多いです。そのため、英語圏の患者さんは服薬時間をきっちり守ろうとする傾向があり、日本人は「だいたい」で済ませてしまうことがある。言語の構造が時間の感じ方を左右している例です。
名詞の性とイメージ
性別を持つ名詞がある言語では、物にも性格を感じやすいといわれます。例えばドイツ語で「橋」が女性名詞の地域では、橋を「優雅」と表現しやすいそうです。日本語にはその感覚がないので、橋はただの橋。こうした違いが認知の微妙な差につながります。
薬局での実例
認知症患者との会話
認知症の方と話すとき、言葉をできるだけ簡潔にすると理解が進むことが多いです。これは、複雑な文構造が認知を混乱させるから。サピア=ウォーフ仮説の観点で見ると、言語のシンプルさが認知の負担を軽くしているわけです。
数量表現の難しさ
高齢者に「1日3回」と伝えても、「いつ飲めばいいんだっけ?」と混乱する方がいます。「朝昼晩で3回ですよ」と言い換えるとすっと理解してくれる。数字の言い方ひとつで認知の負荷が変わるのを実感します。
仮説を日常に活かすには
相手の言語枠を尊重する
相手が普段使っている言語のリズムや表現に合わせると、情報が入りやすくなります。患者さんが「しんどい」と言うなら、その言葉を繰り返しつつ必要な説明を足していく。相手の枠組みを尊重することで、理解も早くなります。
自分の言葉をアップデートする
新しい言い回しや概念に触れると、自分の認知の枠も広がります。私も若いスタッフの言葉遣いを学びつつ、患者さんに合わせて使い分けることで、自分の認知の柔軟性を保つようにしています。
まとめ
サピア=ウォーフ仮説は、言語と認知の深いつながりを示す興味深い考え方です。薬局の現場でも、言葉の選び方が理解や行動を左右する瞬間は多々あります。相手の言語の枠を理解し、自分の表現を工夫することで、より伝わるコミュニケーションが実現できます。言葉を意識するだけで、世界の見え方が少し変わってくるはずです。