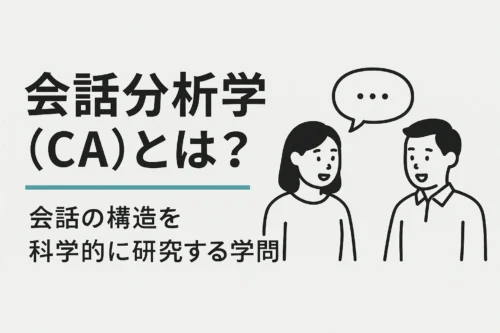毎日40人・年間1万人以上と会話しているRyoです。チーム作業になると急にやる気が消える人、マジでいますよね。心理学ではこれをソーシャルローフィングと呼びます。
みんなでやれば安心という罠
人数が増えると「自分一人くらい手を抜いてもばれない」と感じやすくなる。薬局の棚卸しでも、10人以上集まると一部の人がボーッとしてる。責任の所在がぼやけると、頑張る理由も薄れるんです。
心理の裏側
責任の分散
グループの中では成果が個人に紐づきにくくなる。だから「誰かがやるでしょ」と他人任せになる。私も新人の頃、先輩の影に隠れて適当にやってた時期がありました。今思うとすげー恥ずかしい。
評価の曖昧さ
頑張っても褒められず、サボっても怒られない環境では、やる気は確実に落ちる。評価が曖昧だと、努力のコスパが悪いと感じてしまうんです。
現場での対策
役割を細かく決める
「誰がどこまでやるか」を事前に決めておくと、責任がはっきりする。棚卸しなら「Aさんは1列目、Bさんは2列目」と割り振るだけで、サボりにくくなる。
進捗を見える化
ホワイトボードに進捗を書き出すと、遅れているのが一目でわかる。人は見られてるだけで頑張る生き物なので、公開することが効く。
小さな承認を増やす
終わった作業を報告すると即座に「ありがとう」と返す。地味だけど、承認があるだけで「次もやるか」と気持ちが続く。逆に無視されると一気にやる気が萎える。
一人ひとりが主体になるチームへ
ソーシャルローフィングは誰でも陥る可能性がある。でも、役割と評価をクリアにして、互いに声を掛け合えば、チームの空気は変えられる。面倒でも一手間加えるだけで、全員がちゃんと動くチームになるんです。